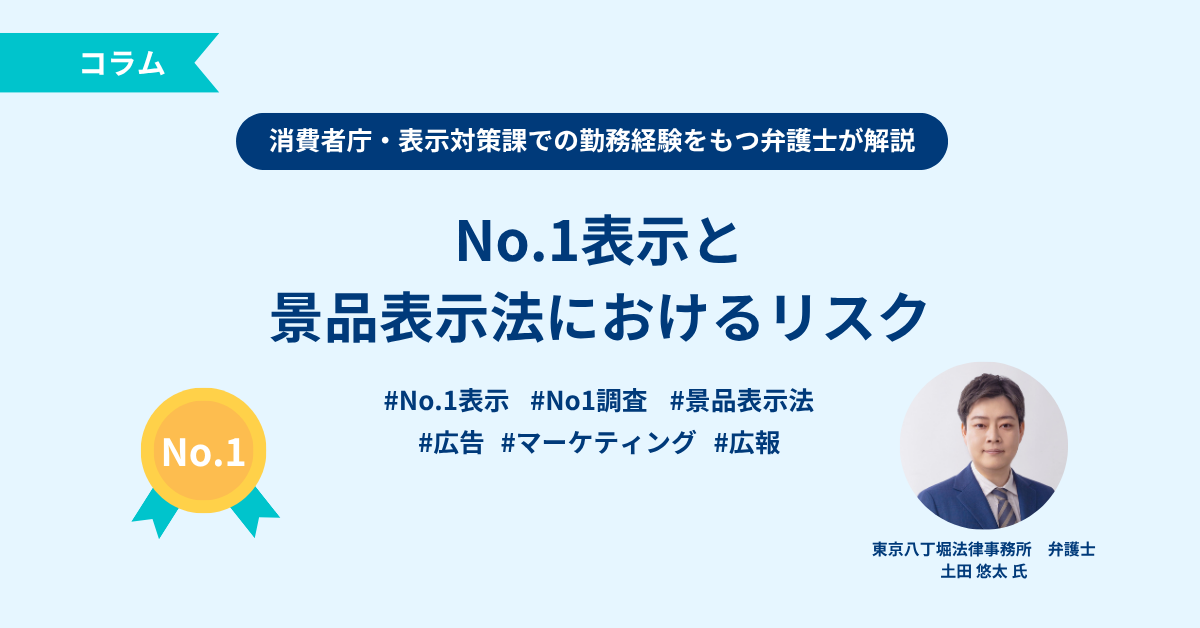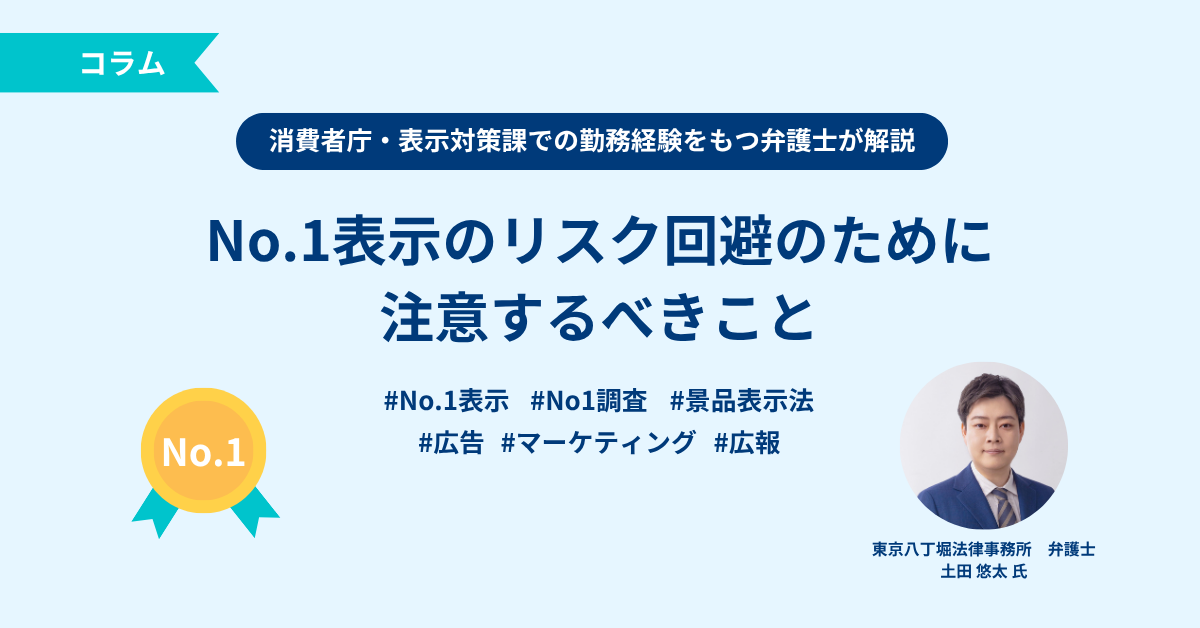No.1表示が違法であるとの指摘を受けてしまったら
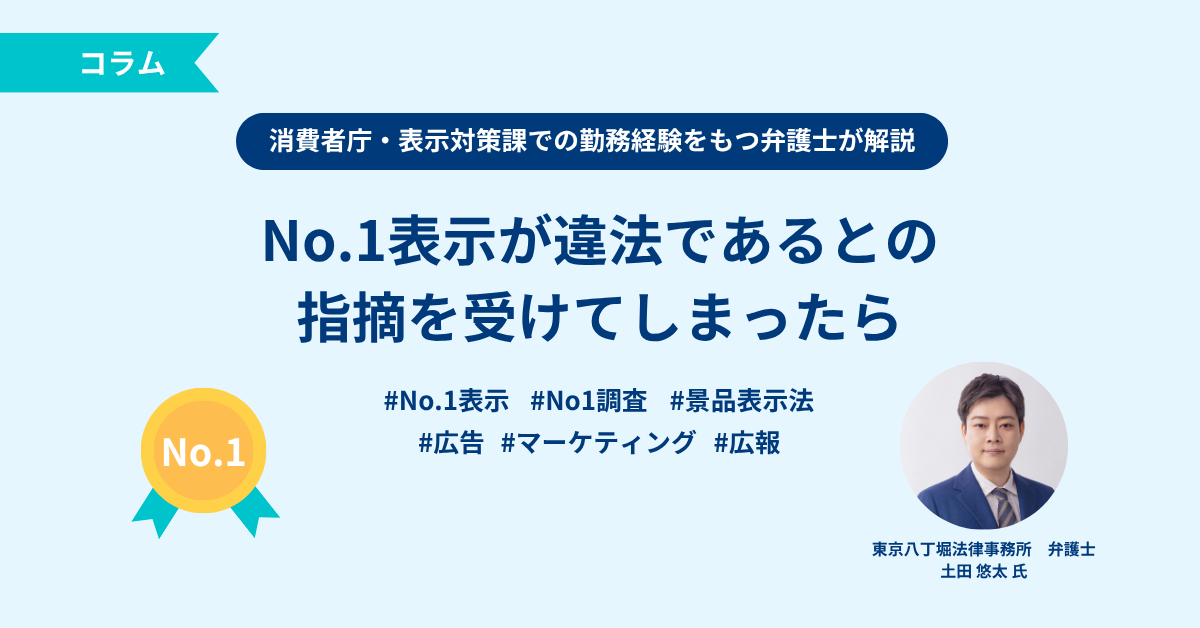
「顧客満足度No.1」「売上第1位」といったNo.1表示は、強力なマーケティング手法である一方、景品表示法違反の疑いで指摘を受けるケースも少なくありません。もし自社の広告が不当表示だと判断された場合、迅速に是正しなければ、課徴金納付命令等の行政処分を受けるだけでなく、返金対応やブランドイメージの毀損といった大きな代償を招きかねません。では、指摘を受けたとき企業は何をすべきなのか? 本コラムでは、No.1表示に問題があるとされた際の実務対応について解説します。
企業が「景品表示法に違反するおそれのあるNo.1表示」を行っていると発覚する場面は様々です。
ここ数年、消費者庁は合理的な根拠のないNo.1表示に対して非常に厳しい目を向けてきました。相次いで行政処分をおこない、2024年9月には「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表して景品表示法上の考え方を整理しました。これにより、世間の注目も一気に高まり、一般消費者や、業界関係者の知識も向上したと考えられます。このような影響を受けてか、社内の従業員が問題に気付いて内部から発覚するというケースや、消費者や業界団体などの外部からの指摘を受けて発覚するというケースも出てきているように思われます。
また、消費者庁からの指摘を受けて発覚するというパターンもあるでしょう。消費者庁の実態調査報告書では、「不当なNo.1表示等が疑われる事案に対しては、迅速に指導を行い是正を図ることを含め、引き続き、景品表示法に基づき厳正に対処していく」と明記されており、積極的に執行を行っていく姿勢が示されています。
実際に、消費者庁が公表した「令和6年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」をみると、その傾向が数字にも表れています。すなわち、令和4年度(2022年度)は112件、令和5年度(2023年度)には85件にとどまっていた「指導」の件数が、令和6年度(2024年度)には339件と飛躍的に増加していることが分かります。このデータからは、報告書で言及されているとおり、消費者庁が、適法性について疑義のあるNo.1表示に対して、積極的に「指導」を行っていることがうかがえます。
指摘を放置することのリスク
もし「景品表示法に違反するおそれのあるNo.1表示」をしているとの指摘を受けた場合、何もしないで放置するという対応は避けるべきです。景品表示法に違反する場合には、消費者庁から行政処分を受けるリスクがあるため、表示の取りやめや、見直しの要否を迅速に検討する必要があります。
ここで注意すべきは、上記のとおり、消費者庁が積極的に「指導」をおこなっているという現状は、行政処分を受けるリスクが軽減されたことを意味するものではないということです。2025年9月26日現在、実態調査報告書の公表後に、No.1表示について新たに措置命令が行われたという事例は見当たりませんが、個別の事案に応じて、「指導」ではなく、措置命令が検討される可能性は十分に想定されるでしょう。
なお、景品表示法は、令和5年(2023年)の改正により確約手続を導入し、令和6年(2024年)10月1日から施行されています。この制度は、景品表示法に違反する疑いのある表示を行っているとして、消費者庁の調査を受けた事業者が、当該表示を自主的に是正し、再発防止策を講ずるなどの計画(確約計画)を策定し、消費者庁の認定を受けた場合には、行政処分を受けることを回避できるというものです。
一見すると、企業に優しい制度のように映りますが、実際には必ずしも優しい制度というわけではありません。たとえば、令和7年(2025年)9月には、No.1表示が調査対象とされていた事案で、確約計画の認定がされました。公表資料によれば、イメージ調査を根拠に「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービスNo.1」などのNo.1表示を行っていたという事案のようですが、確約計画では、当該表示がされていた商品を購入した消費者に対して代金の一部を返金するという内容が盛り込まれています。返金対象期間は約3年8か月に及んでおり、金銭的な負担は相当な規模になる可能性があります。指摘を放置することは、いざ確約手続を利用することとなった場合に、返金額を増大させる結果にも繋がりかねず、留意が必要です。
何をすべきか?
それでは、実際に指摘を受けた場合には、企業としてはどのような対応をとるべきでしょうか。
まずは、No.1表示の根拠について確認をすることが重要な一歩となります。具体的には、No.1表示の裏付けとなる調査が実施されていたか、仮に実施されている場合には、当該調査の内容はどのようなものであったかを確認する必要があります。調査資料が保管されていない場合でも、調査を実施した調査業者であれば資料を保管している可能性がありますから、速やかに照会することが望ましいでしょう。
次に、実施されている調査が、No.1表示を裏付ける「合理的根拠」として認められるかどうかを冷静に分析、判断する必要があります。「顧客満足度No.1」など第三者の意見や感想を指標とするNo.1表示については、消費者庁の実態調査報告書で示された基準を満たしているといえるか、チェックをすることが重要です。
※調査の内容が、No.1表示の裏付けとなる合理的な根拠と認められるかどうかを判断する基準については、「1表示のリスク回避のために注意するべきこと」のコラムにおいて詳しく説明しています。あわせてご参照ください。
仮に、景品表示法に違反する可能性があると判断される場合は、表示の取りやめや、見直しを実行する必要があります。調査の実施時期が数年前にさかのぼるようなケースでは、単なる「イメージ調査」を根拠にNo.1表示を行ってしまっているケースもあり得ます。このような場合は、不当表示に当たる可能性は極めて高いといえ、迅速に是正する必要があるでしょう。
なお、インターネット上の広告は、複数の媒体に残存している可能性があります。表示を是正する際には、不当表示が発覚した媒体だけでなく、その他の媒体についても念入りに点検することが適切です。適法性の判断や、対応方針に悩みが生じた場合には、景品表示法に詳しい専門家に相談するという方法も選択肢に入れるとよいでしょう。
指摘を受けないために
もっとも、企業にとって最も望ましいことは、そもそも「不当表示の疑いがある」と指摘される事態を招かないことです。指摘を受けてから対応するよりも、事前に適法性を確保しておく方が、時間的・金銭的コストのみならず、ブランドイメージへの影響も大幅に抑制することができます。
過去2回のコラムでも触れたように、No.1表示をおこなう場合には、合理的な根拠と認められるだけの裏付け調査を実施する必要があります。調査設計の粗さに目を瞑れば、一時的には調査コストを下げられるかもしれません。しかし、その代償として景品表示法違反のリスクが高まれば、最終的にかかるコストは莫大なものとなり得ます。
No.1表示は、適切に実施すれば強力なマーケティング手法として機能します。しかし、裏付けが不十分であれば、一転して大きなリスク要因となります。だからこそ企業には、調査設計の段階から適法性を意識し、適正な根拠に基づいてNo.1表示を行う姿勢が求められます。これこそが、消費者の信頼を維持しつつ、持続的なブランド価値を形成するための最善の道といえるでしょう。