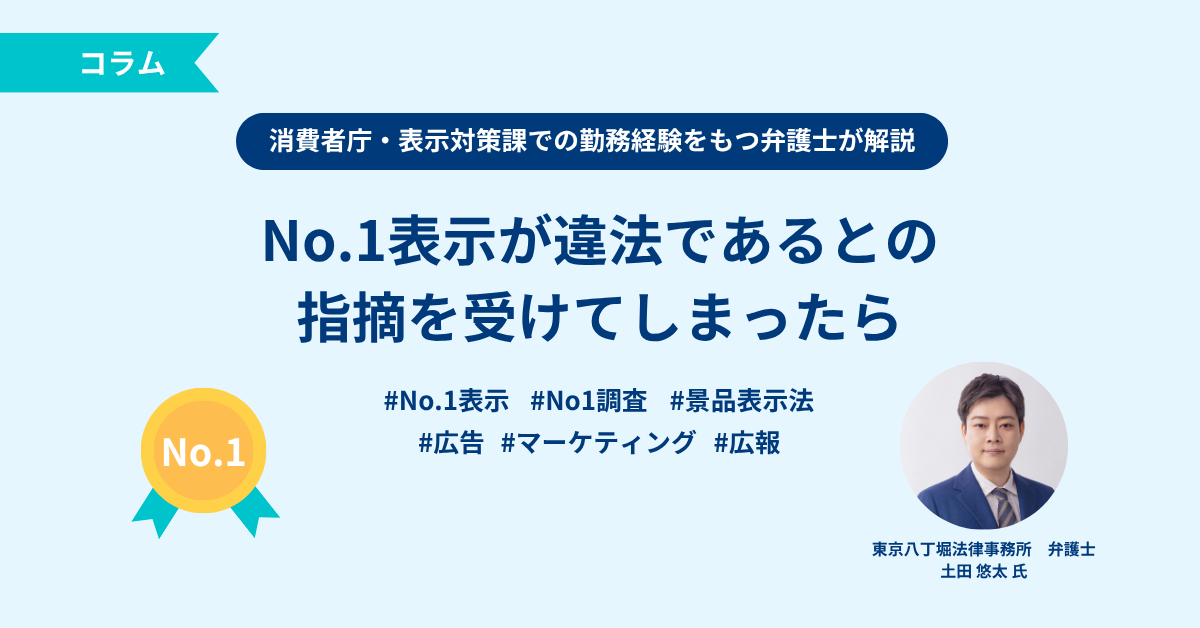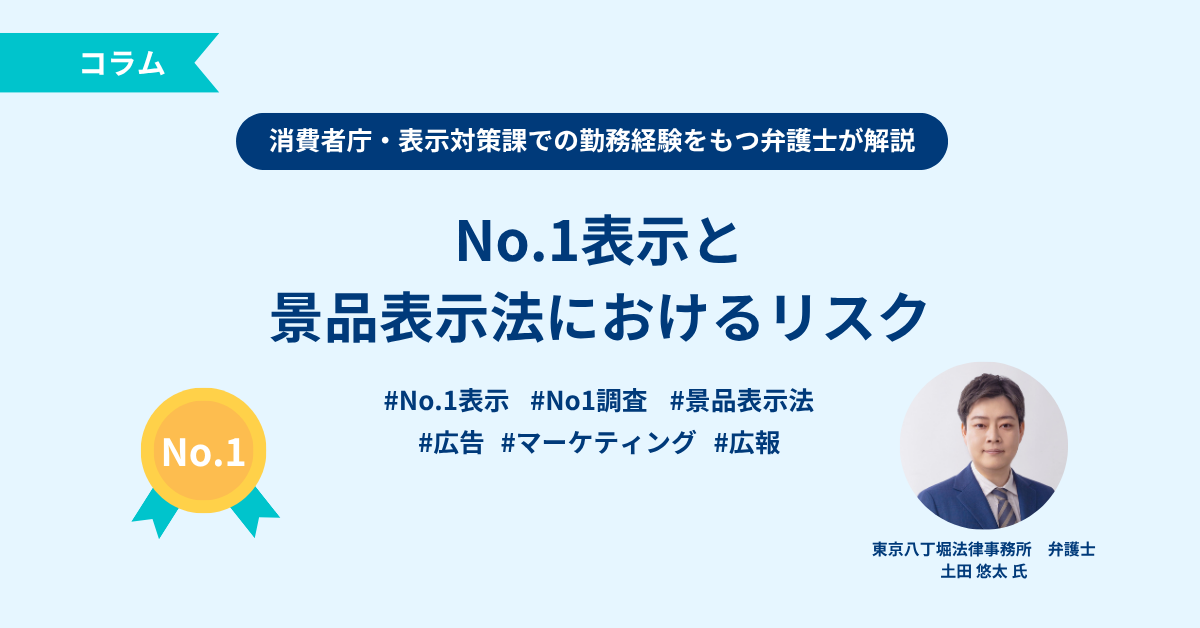No.1表示のリスク回避のために注意するべきこと
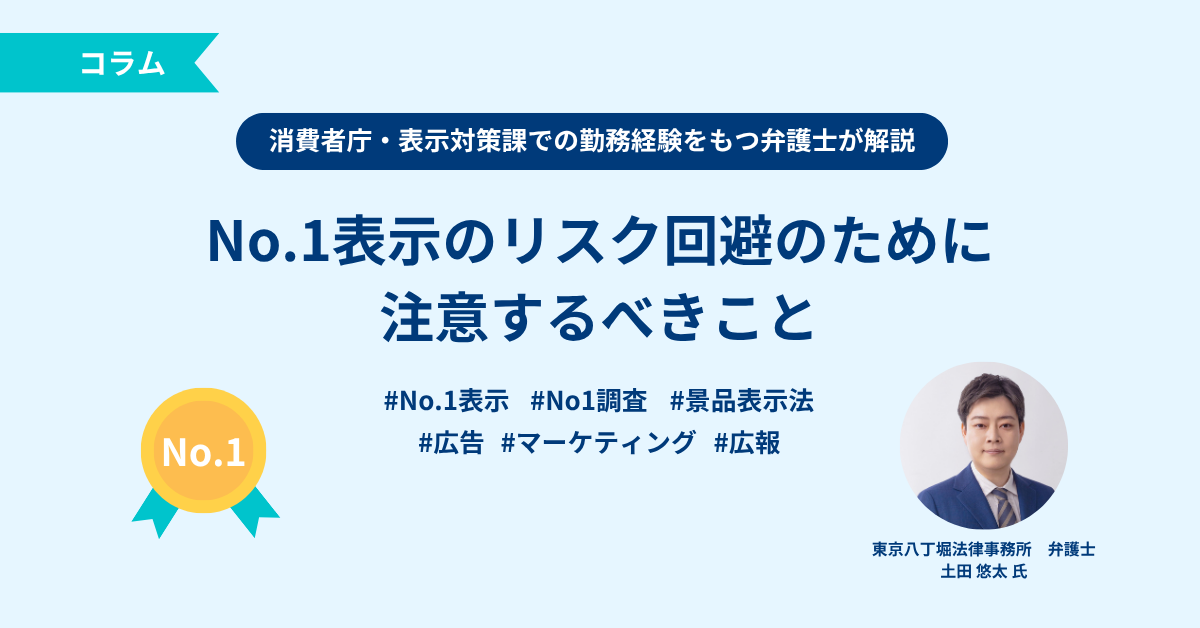
「顧客満足度No.1」「売上第1位」――消費者の購買意欲を高める強力なキャッチコピーとして、多くのマーケティング施策で活用されています。しかし、確かな裏付けがなければ景品表示法違反にあたるリスクがあります。根拠となる調査の設計においては、比較対象の選定や調査対象者の属性、調査方法の公平性といったポイントを誤ると、「不当表示」と判断される可能性が高まります。本コラムでは、消費者庁が示す基準をもとに、No.1表示のリスク回避のための実践的チェックポイントを解説します。
不当なNo.1表示とならないためのチェックポイント
No.1表示は、裏付けとなる合理的な根拠がなければ、あたかも実際のものよりも優れている商品・サービスであるかのように一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となるリスクがあります(景品表示法については、過去のコラム「No.1表示と景品表示法におけるリスク」をご参照ください。)。
「顧客満足度No.1」のように、第三者の意見・感想(主観的評価)を指標とするNo.1表示をおこなう場合には、アンケート調査やヒアリング調査を実施して、回答者の意見や感想を調査する場合が多いでしょう。消費者庁の『No.1表示に関する実態調査報告書』では、このような調査がNo.1表示の合理的な根拠として認められるには、少なくとも次の①から④までの基準を満たしている必要があると指摘されています。
① 比較する商品・サービスが適切に選ばれていること
② 調査対象者が適切に選ばれていること
③ 調査が公平な方法で実施されていること
④ 表示内容と調査結果が適切に対応していること
※消費者庁『No.1表示に関する実態調査報告書』はこちらで読むことができます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_02.pdf
比較する商品・サービスの選定(上記①)
No.1表示とは、その言葉のとおり、競争事業者の商品・サービス(以下では「ライバル商品」といいます。)と比較して、その商品・サービスが第1位であることを示すものです。したがって、No.1表示の裏付けとなる調査が、合理的な根拠といえるためには、少なくとも、比較対象に主要なライバル商品をきちんと含める必要があります。
実態調査報告書では、たとえば次のようなケースは、景品表示法上、問題となるおそれがあると指摘されています。
- 「○○サービス 満足度No.1」などと表示する場合において、市場における主要なライバル商品を比較対象に含めないまま調査を行っている場合
- インターネット検索により、単に検索結果で上位表示されたライバル商品を比較対象としているだけで、市場における主要なライバル商品を比較対象に含めないまま調査を行っている場合
比較するライバル商品として、インターネット検索で上位表示されたものだけを選んでいるケースは、しばしば見られます。しかし、上位表示される商品が、そのまま市場における主要な商品であるとは限りませんので、比較対象に漏れがないかはチェックする必要があるでしょう。
また、No.1表示の中には、たとえば「比較対象企業選定条件:『○○』で検索上位○社(Google)」などのように、調査方法についての注記がされている例をみることもありますが、このような注記をしているからといって、免罪符になるわけではありません。実態調査報告書においても、「記載位置、文字の大きさ、文字の色等を踏まえ、一般消費者にとって明瞭でない方法により注記がされている場合」は、景品表示法上問題となるおそれがあると指摘されており、留意する必要があるでしょう。
調査対象者の選定(上記②)
第三者の意見・感想(主観的評価)を調査して、No.1表示の根拠とする場合、調査対象者の選び方が極めて重要です。とくに、第三者の主観的評価を調査する場合には、「売上額」のような客観的数値と違い、調査が恣意的に設計されたり、回答者のバイアスが働く可能性があるため、注意する必要があります。
実態調査報告書では、たとえば次のようなケースは、景品表示法上、問題となるおそれがあると指摘されています。
- 自社の商品・サービスを継続的に購入している顧客だけを選んで調査を行う場合
- 自社の社員や関係者を選んで調査を行う場合
また、No.1表示をみたときに、一般消費者が認識するであろう回答者の属性と、実際の回答者の属性が乖離していないか、という点も重要なチェックポイントとなります。たとえば、「顧客満足度No.1」という表示を見た一般消費者は、特段の事情がないかぎり、その商品・サービスを実際に利用したことがある者にアンケートをとっていると認識するものと考えられます。したがって、アンケートの回答者について、調査対象となる商品・サービスの利用経験の有無を確認せずに調査がおこなわれている場合には、景品表示法に違反する可能性が高いといえます。
近年、消費者庁は、「イメージ調査」と呼ばれる調査を根拠に、「顧客満足度No.1」などと表示している事業者に対して、相次いで行政処分を行いました。これらの事例についても、表示内容との関係で、調査対象者の選び方に問題があったと理解することができます。
※ 「イメージ調査」とは、回答者が、調査の対象となる商品や、これと比較する商品(競合他社の商品)を使用した経験の有無を確認せずにおこなうアンケート調査のことをいいます。アンケートの回答者には、これらの商品を提供する各事業者のウェブサイトなどを見せた上で、たとえば、「ご覧いただいたサイトの中で、顧客満足度が高いと思う商品を選んでください。」などと質問するのが典型的です。
なお、商品・サービスの性質や、具体的な表示内容によっては、単に商品を購入したり、利用経験がある者を回答者に選ぶだけでは十分ではない場合があります。たとえば、一定の保険商品の「顧客満足度」を調べる場合には、単に保険に加入している者ではなく、実際に保険適用を受けたことがある者を回答者に選ぶべきケースがあり得るでしょう。保険適用を受けていない段階では、その保険商品の満足度を適切に評価することはできないと考えられる場合があるからです。この点は、実態調査報告書においても記載されており、留意する必要があるでしょう。
調査方法の公平さ(上記③)
調査内容の客観性を担保するためには、調査方法についても、調査者による恣意性や、回答者のバイアスを排除し、公平な調査を実施する必要があります。実態調査報告書では、たとえば次のようなケースは、景品表示法上、問題となるおそれがあると指摘されています。
- 自社に有利になるよう回答を誘導する場合
- 自社の商品・サービスが第1位になるまで調査を繰り返している、1位になったタイミングで調査を終了するなど、結論ありきの調査がおこなわれている場合
1つ目の回答の誘導については、たとえば、複数の商品・サービスの中から「おすすめしたいもの」を選んで回答させるという場合に、自社の商品・サービスを選択肢の最上位(先頭)に固定して、選択されやすくするような手法は公平とはいえません。選択肢がランダムに表示されるような手法をとるなど、適切な方法がとられているかチェックする必要があるでしょう。
表示内容と調査結果の対応(上記④)
上記①から③までの基準とも関わる話となりますが、表示内容と、調査結果は適切に対応している必要があります。たとえば、全国展開をしているサービスについて、一定の地域で「顧客満足度No.1」を取得したとしても、全国でみたときに第1位ではない場合には、あたかも全国で第1位であるかのように表示することはできません。
不当表示のリスクを回避するために
ここまで見てきた①から③までの基準は、いずれも調査設計に関わる事項です。したがって、不当表示のリスクを回避するためには、調査業者が、これらの基準を理解したうえで、調査設計を適切に行っているかどうかをチェックすることが重要です。
もし調査内容に疑問があれば、調査業者に積極的に確認し、納得できる説明を受けるべきです。また、調査設計などにあたって調査業務の専門家や、景品表示法の専門家などが関与しているかどうかを確認することも、リスクを軽減するうえで有効といえるでしょう。このように、業者任せにせず、広告主自らが確認とチェックを怠らないことが、不当表示のリスクを回避する上では非常に重要です。