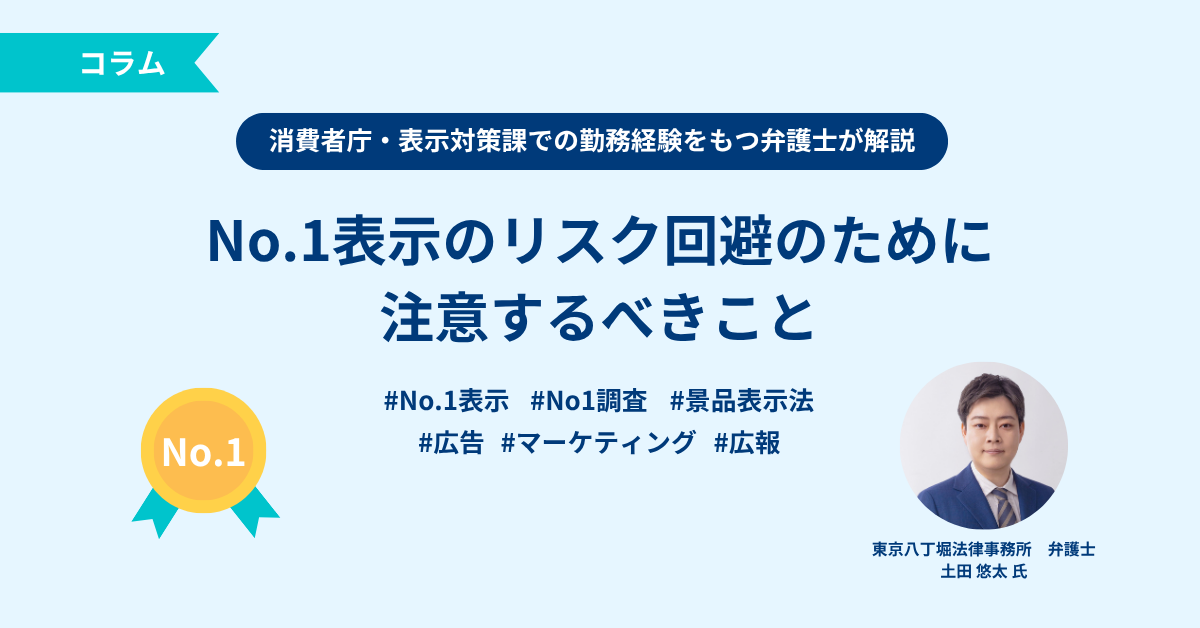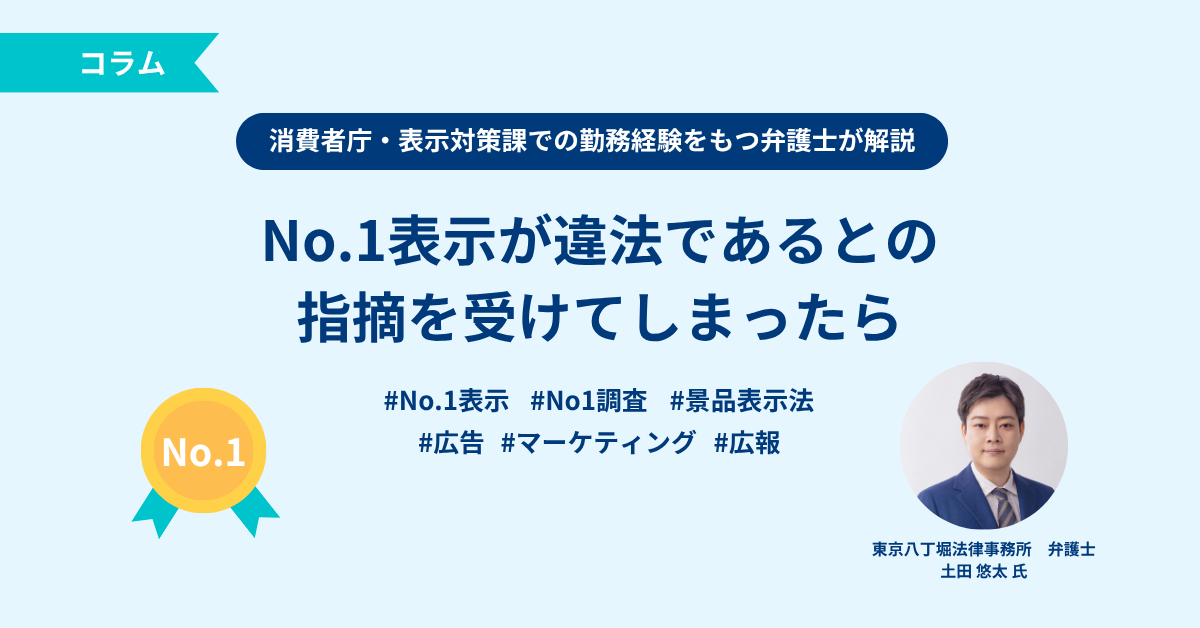No.1表示と景品表示法におけるリスク
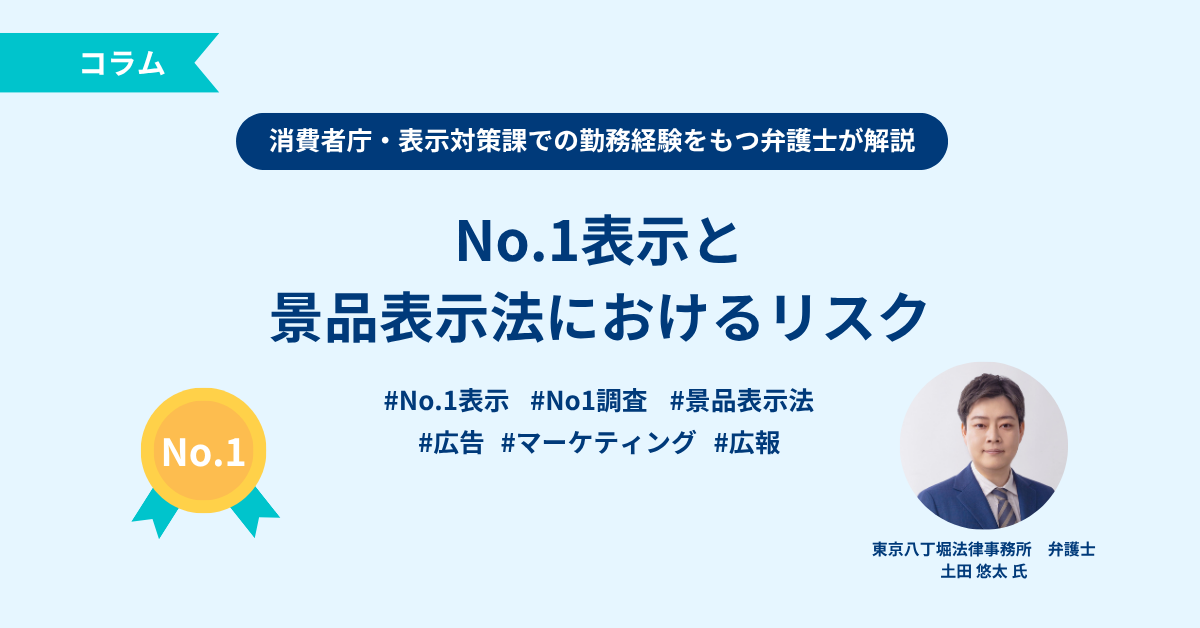
広告やマーケティングでよく目にする「No.1」。売上拡大やブランド強化に効果的な一方で、根拠のないNo.1表示は景品表示法違反のリスクを招き、課徴金納付命令等の行政処分や、企業イメージの失墜につながりかねません。近年は消費者庁による摘発事例も増えており、企業にとっては見逃せない重要課題です。本コラムでは、景品表示法に違反するNo.1表示とはどのようなものか、不当なNo.1表示のリスクについて分かりやすく解説します。
No.1表示とは?
商品やサービスの広告において、「売上第1位」、「顧客満足度No.1」などといったフレーズを見かけたことはありませんか?こうした表現は、自社の商品やサービスが、特定の指標(上記の例では、「売上」や「顧客満足度」)において、競合他社のものよりも優れていることを強調するものです。これらは一般に「No.1表示」(ナンバーワン表示)と呼ばれています。
No.1表示は、一般消費者にとっては、商品・サービスを選択するうえで参考になる情報であり、企業にとっても、自社の強みを分かりやすくアピールできる有力なマーケティング手法です。実際に、消費者庁が2024年に実施した実態調査によれば、新しい商品・サービスを購入する際に、No.1表示が購入の意思決定に「かなり影響する」または「やや影響する」と回答した者は、全体の約5割を占めました。消費者庁は調査結果をとりまとめた『No.1表示に関する実態調査報告書』において、「No.1表示が消費者行動に与える影響は大きい」と結論づけています。
※消費者庁『No.1表示に関する実態調査報告書』はこちらで読むことができます。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_02.pdf
消費者庁による摘発も!――「No.1表示」が違法となるリスク
このように、No.1表示とは、本来、一般消費者にとっても、企業にとっても有益な情報提供のツールとなり得るものです。しかし、No.1表示のもつ効果を期待して、根拠が不十分であるにもかかわらず「No.1」と称する広告が出現することとなり、社会問題となっていました。
とくに、「顧客満足度No.1」、「コスパが良いと思う○○第1位」といった、第三者の意見や感想(主観的評価)を指標とするNo.1表示の中には、No.1を裏付けるだけの調査が十分におこなわれていないものも数多く見られる状況でした。
このような背景の中で、消費者庁は近年、合理的な根拠がないままに「顧客満足度No.1」などの表示をおこなうことは景品表示法に違反するとして、相次いで行政処分をおこないました。さらに、2024年9月には、先述の実態調査を実施し、第三者の意見や感想(主観的評価)を指標とするNo.1表示について、不当表示をおこなわないよう注意を促しています。
景品表示法による規制
景品表示法とは、一般消費者がよりよい商品・サービスを安心して選ぶことができるように、一般消費者を誤認させる表示を規制する法律です。この法律では、実際の商品・サービスよりも、品質や内容が著しく良いものであるかのように示す表示(優良誤認表示)や、実際の価格や取引条件よりも、著しく「お得」な内容であるかのように示す表示(有利誤認表示)が、不当表示として禁止されています(景品表示法5条1号・2号)。
たとえば、「着るだけで痩せるシャツです!」などと謳いながら、実際には表示どおりの痩身効果を得ることができない場合などが、不当表示にあたる典型的なケースです。このような表示が横行してしまうと、一般消費者は、不当表示の内容を信じてしまい、よりよい商品・サービスを選ぶことができなくなってしまうおそれがあります。そのため、景品表示法による規制がされているのです。
No.1表示についても、きちんとした根拠がないまま「No.1」を謳っている場合には、不当表示にあたるおそれがあります。たとえば、ある商品について「売上第1位」と表示をしているのに、実際の順位が2位や3位であった場合には、景品表示法に違反する(優良誤認表示に該当する)おそれがあります。
消費者庁が問題視するNo.1表示
近年、消費者庁が行政処分をおこなったNo.1表示には、いくつかの共通点がありました。第一に、いずれの事例においても、「顧客満足度No.1」などのように、第三者の意見や感想(主観的評価)を指標とする表示が問題とされました。第二に、これらの表示は、いずれも「イメージ調査」と呼ばれる調査の結果を根拠とするものでした。
イメージ調査というのは、回答者が、調査の対象となる商品や、これと比較する商品(競合他社の商品)を使用した経験の有無を確認せずにおこなうアンケート調査のことをいいます。アンケートの回答者には、これらの商品を提供する各事業者のウェブサイトなどを見せた上で、たとえば、「ご覧いただいたサイトの中で、顧客満足度が高いと思う商品を選んでください。」などと質問するのが典型的です。
しかし、一般消費者からすると、「顧客満足度No.1」などと表示されれば、実際にその商品を利用した経験のある方がアンケートに回答していると思うのが通常でしょう。そのため、一般消費者は、その商品が、多くの利用者にとって満足度が高い商品(=良い商品)であったと認識するものと考えられますが、実際には、ウェブサイトを閲覧した際の印象(まさに、イメージ)を尋ねるだけの調査が行われているに過ぎないのです。
消費者庁は、このようなイメージ調査が実施されていたとしても、「顧客満足度No.1」などの表示を裏付ける合理的な根拠とはならず、不当表示に当たると判断し、行政処分をおこなっています。
不当なNo.1表示が蔓延する背景
このような不当なNo.1表示が、世の中に蔓延してしまった背景には、どのような事情があったのでしょうか。この点に関して、消費者庁の実態調査報告書では、景品表示法を十分に理解していない調査会社や、コンサルティング会社が、イメージ調査によるNo.1表示を積極的に勧めているケースがみられたことが指摘されています。
報告書では、実際に勧誘を受けたという企業に対するヒアリング調査の結果が、生々しく記載されています。それによれば、「不当表示のリスクが無いよう、No.1の裏付けとなる合理的な根拠を取得し納品します」という説明や、「顧問弁護士がリーガルチェックをしているので安心してほしい。」という説明を受けて安心していたという声や、調査に要する費用が非常にリーズナブルであったため魅力に感じたという声が記載されています。
企業にとってのリスクは甚大
No.1表示が景品表示法に違反すると認定された場合には、消費者庁から行政処分を受けるリスクがあります。具体的には、不当表示の停止などを求める「措置命令」や、金銭的なペナルティである「課徴金納付命令」を受けることがあります(ただし、不当表示がされた商品の売上額が5,000万円未満の場合など、例外的に課徴金の対象外となる場合があります。)。課徴金については、不当表示がされた商品・サービスの売上額の3%を国庫に納付しなければなりません。その金額は数千万円から数億円にのぼるケースもあり、企業にとっては深刻な経済的打撃となり得ます。
また、これらの行政処分を受けたという事実は、消費者庁のウェブサイトで公表され、新聞やネットニュースなどで大きく取り上げられます。企業名が報道で繰り返し言及されることになり、ブランドイメージが大きく損なわれるリスクもあるでしょう。
一般消費者の信頼は、一度失えば容易には回復しません。こうしたリスクの大きさを踏まえれば、No.1表示をおこなう際には、表示を裏付ける合理的な根拠と認められるよう、適切に調査を行うことが不可欠です。そのためには、信頼できる調査業者をパートナーに選ぶとともに、自らも積極的に、調査が適切に実施されているかを確認する姿勢が重要といえるでしょう。