研究者必見!学術調査(アカデミックリサーチ)の手法・メリット、おすすめ調査会社7選

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
近年、研究開発や事業戦略の高度化に伴い、学術調査(アカデミックリサーチ)の重要性がますます高まっています。論文執筆や新規研究テーマの立案だけでなく、ビジネスシーンにおいても科学的根拠に基づく調査活動は不可欠です。
とはいえ、多様な手法や専門的な分析プロセス、調査会社の選択肢が増える中、自社に適した調査アプローチを見極めることは容易ではありません。
本記事では、学術調査の定義や役割、主な実施手法などを詳しく解説します。おすすめの調査会社も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
学術調査とは
学術調査とは、学問的な探究を目的として行われる調査活動のことを指します。研究者や学生が客観的なデータを収集し、理論や仮説を検証するために行う重要なプロセスです。
ここでは、学術調査の定義と役割に加え、マーケティング調査との違いについても深掘りしていきましょう。
学術調査の定義と役割
学術調査は、主に研究者や教育機関が学術研究や論文執筆を目的として実施する調査です。研究テーマに関連する客観的なデータを収集および分析することで、仮説の検証や新たな知見の創出を目指しています。
学生の卒業論文や修士論文、研究機関での実証研究など、幅広い学術分野で活用されています。
マーケティング調査との違い
学術調査で重視されるのは、「科学的に正しいかどうか」です。そのため、調査上のルールが明確で、誰がやっても同じ結果が出ることが求められます。いっぽう、マーケティング調査で重視されるのは「意思決定に役立つかどうか」で、実践的な課題解決や市場判断につながる情報を重んじます。
このように、目的と成果の評価軸が異なる点が学術調査とマーケティング調査の大きな違いです。
学術調査の主な手法
学術調査には多様な手法があり、研究目的や調査対象に応じて適切な方法を選択する必要があります。
代表的な手法とそれぞれの特徴は、以下の通りです。
| 手法 | 特徴 |
|---|---|
| ネットリサーチ | ・比較的低予算での大規模調査が可能 ・短期間で多くの回答を効率的に収集できる ・時間や場所を問わず匿名性が高いためセンシティブなテーマにも対応可能 |
| グループインタビュー | ・複数人の意見を同時に収集できる ・調査者がリアルタイムで参加者の反応を観察できる ・新たな視点やアイデアを創出しやすい |
| 会場調査 | ・一定の場所に対象者を集めて調査を行うため質の高いデータ収集が可能 ・実際の行動観察や詳細なヒアリングも併用できる ・物理的な準備が必要でコストや時間がかかる |
| 郵送調査 | ・アンケートと回答を郵送で行う伝統的調査手法 ・インターネットが使えない層や地域にも対応可能 ・回収までに時間がかかるうえ回収率が低下しやすい |
| 海外調査 | ・複数国で同時に調査を実施可能 ・国際比較研究に有効 ・言語や文化の違いに対応するために専門知識が必要 |
近年は、迅速かつ効率的にデータを収集できることから、学術調査においてネットリサーチが広く活用されるようになってきています。
なぜ学術調査にネットリサーチが選ばれるのか?3つのメリット
先述したように、近年の学術調査で広く活用されるようになってきているのはネットリサーチです。ここでは、学術調査にネットリサーチを選ぶ3つのメリットを解説します。
大規模データを短期間で収集できる
ネットリサーチは、大規模なデータのサンプルをスピーディーに回収できるのが大きな利点です。オンラインでの配信により、広範囲かつ多様な属性のデータを短期間で収集できる点が、学術調査の迅速性に大きく貢献しています。
コストを抑えながら幅広い対象に調査できる
ネットリサーチは、物理的コストが不要です。そのため、調査票の配布が必要な「郵送調査」や、会場準備が不可欠な「グループインタビュー」などに比べて低予算で実施できます。地域や属性を限定せず、幅広い対象へ効率的にアクセスできるのがメリットです。
回答しやすく幅広いテーマに対応できる
ネットリサーチは匿名性が高く、なかなか自分の意見を言えないセンシティブなテーマでも回答を得やすい特徴があります。加えて、海外パネルを活用することで国際比較調査にも展開できるため、多様な研究テーマへの対応が可能です。
学術調査にネットリサーチを利用する際の注意点

メリットが多いネットリサーチですが、学術調査に利用するうえでの注意点もしっかりと押さえておきましょう。
サンプルに偏りが出やすい
ネットリサーチは、基本的にインターネット利用者を対象にしています。そのため、高齢者をはじめとするインターネット非利用者のデータが不足しがちで、調査対象に偏りが生じることが避けられません。
高齢者層のネット利用率は増加傾向にあるものの、依然として一部層は調査対象外となる可能性が高いです。結果を解釈する際には、慎重な補正や分析を心がけましょう。
回答の質が一定でない
ネットリサーチでは、報酬目的の虚偽回答や、意図的な不正回答が混入するリスクがあります。また、操作を間違えたことによる誤回答や、対象者以外が代わりに回答するケースも少なくありません。
調査設計の段階で誤入力の修正や重複データの削除といった「データクリーニング」を行い、信頼性のあるデータを確保する対策が必要です。
学術調査の主な具体例一覧
学術調査は、さまざまな分野で実施されています。各分野ごとの代表的な調査テーマは、以下の通りです。
| 分野 | 具体例 |
|---|---|
| 教育分野 | 学習習慣や生活実態に関する調査 |
| 医療・健康分野 | 生活習慣病予防や患者満足度の調査 |
| 心理学・行動科学 | 被験者実験や観察による行動検証 |
| 政策研究 | 少子化問題や環境問題に関する市民意識調査 |
| 国際比較研究 | 日本と海外の生活者意識や文化の比較調査 |
| 卒論研究 | 学生によるアンケートやインタビューを用いたテーマ検証 |
教育や医療、心理学などの専門的な研究だけでなく、社会政策や国際比較といった社会全般の課題解決にも活用されています。
学術調査の方法は大きく分けて2種類

学術調査は、大きく分けると「調査会社に依頼する方法」と「セルフリサーチ」の2つに分類されます。それぞれの調査方法の特徴を見てみましょう。
調査会社に依頼
専門の調査会社に設計からデータ回収、分析まで一括して依頼する方法です。調査設計の専門知識を持つリサーチャーが企画段階からサポートしてくれるため、調査の品質や信頼性が高まります。
調査の実施から集計・分析までワンストップで対応してもらえるため、研究者の負担が軽減されるのがメリットです。一方で、コストがかかることやスケジュール調整が必要になる点がデメリットとして挙げられます。
特に、複雑な設問設計や大量のデータ処理が求める場合に向いています。
アンケートツールを用いたセルフリサーチ
研究者自身がオンライン上のアンケートツールを利用して、調査の設計・配信・回収を行う「セルフリサーチ」の方法もあります。導入コストを抑えられ、スピーディーに調査が進められる点が大きなメリットです。
近年は操作性に優れたツールも増え、専門知識が少なくても対応可能になっています。ただし、調査設計の不備や回収管理の難しさ、複雑な分析機能が限定的であることがデメリットとして挙げられます。調査経験の浅い研究者にとっては、データの質を確保するための工夫が欠かせません。
【関連記事】ネットでできるセルフリサーチ|メリットやアンケートツールの選び方、おすすめサービス8選も
学術調査におすすめの調査会社7選
複雑な設問設計や大量のデータ処理が求められる場合には調査会社に依頼するのが望ましいです。学術調査に強みを持つ調査会社を紹介しますので、比較検討の際の参考にしてください。
マイボイスコム株式会社
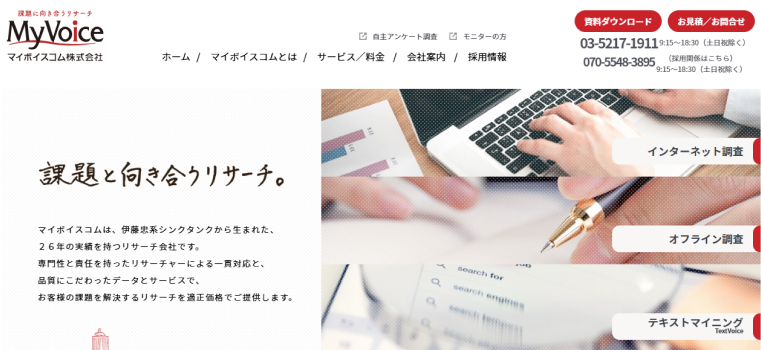
参照元:マイボイスコム株式会社
マイボイスコムは、専門のリサーチャーが調査設計から結果報告までを一貫して行う「コンサル型リサーチ」を強みとしている調査会社です。
学術調査においては依頼の4割以上が大学や研究機関からで、これまで300以上の高等教育機関から依頼を受けた実績を持っています。オンラインだけでなくオフライン調査も提供しており、過去3年間の顧客満足度は95%を誇ります。
株式会社日本リサーチセンター

参照元:株式会社日本リサーチセンター
日本リサーチセンターは、1960年創業の老舗調査会社で、ISO9001・ISO20252の認証取得による高品質管理を強みとしています。
調査設計から集計や分析、レポート作成までワンストップの対応が可能で、全国訪問調査「NOS」など独自の調査サービスを展開しているのが特徴です。長年の経験と実績を活かした多様な調査手法で、企業や官公庁、大学など幅広い業種・業界での調査に貢献しています。
株式会社クロス・マーケティング

参照元: 株式会社クロス・マーケティング
クロス・マーケティングは、国内外問わず学術調査や官公庁のリサーチ案件を多数手がけている総合調査会社です。社内には学術調査専門チームが設置されており、大学や研究機関、自治体、公共団体などの調査業務を包括的に支援しています。
累計10,000件を超える学術案件の実績を持ち、その多くが論文掲載に採用されるなど研究データとしての信頼性の高さが評価されています。
株式会社ネオマーケティング

参照元: 株式会社ネオマーケティング
ネオマーケティングは、国内外のネットリサーチをはじめ、デプスインタビュー、グループインタビューなど、定量・定性のいずれの調査にも対応できる柔軟性の高いリサーチ会社です。
最短3営業日での迅速な対応が強みで、累計取引実績3,000社以上、年間支援件数1,500件以上という豊富なプロジェクト経験を有します。
独自のフレームワークを取り入れながら、調査票作成・データ分析・ワークショップ企画など、調査に関わる全工程を一括して支援しています。
株式会社NeU

参照元: 株式会社NeU (ニュー)
NeUは、東北大学と日立グループが共同出資した脳科学ベンチャーで、学術分野における高度な生体計測リサーチを専門としています。
自社開発の「fNIRS(近赤外分光法)」を用いた脳活動測定を中心に、アイトラッキング・心拍・瞳孔・皮膚電位・唾液成分など、多様な生体データを組み合わせた研究支援が可能です。
大学や研究機関との共同プロジェクトや企業の新製品開発に関連する実証試験にも多数参画しており、機能性食品臨床試験など通常は調査が難しい分野においても実績があります。科学的根拠に基づいた高精度なリサーチをスピーディに実施できる点が大きな強みです。
日本インフォメーション株式会社

参照元: 日本インフォメーション株式会社
日本インフォメーションは、1969年創業の独立系リサーチ会社です。学術調査をはじめとする幅広い分野の調査を手掛けており、会場調査(CLT)の年間実施数は約600件、ホームユーステスト(HUT)も年間200件以上と業界トップクラスの実績を誇ります。
「機縁リクルート」と「WEBリクルート」の2つの手法を活用した大規模なネットワークを持ち合わせており、他者では難しい複雑なリサーチにも対応できる点が強みです。
楽天インサイト株式会社

参照元: 楽天インサイト株式会社
楽天インサイトは、楽天グループのデータ資産を活用したネットリサーチを実施する調査会社です。学校法人や公的機関、官公庁との取引数は年間約170社にのぼり、研究目的の学術調査を数多く支援しています。
自社で保有する約220万人規模の高品質パネルを活用し、幅広い層を対象に調査を行える点が強みです。
学術調査は手法と調査会社選びが重要
学術調査では、自身の研究目的に合った手法の選択が成果に直結します。主な手法として挙げられるのは、ネットリサーチ・グループインタビュー・会場調査・郵送調査・海外調査です。
また、 調査の品質や信頼性を高めるためには、依頼する調査会社選びも重要なポイントです。質の高い学術調査を実施するためにも、手法と調査会社選びは慎重に行いましょう。
リサーチ会社探しにお困りなら
調査会社マッチング
貴社の課題をヒアリングし、課題解決に最適なリサーチや調査会社をご紹介するサービスです。
調査会社選びにお困りなら是非ご相談ください。



