エスノグラフィーをわかりやすく解説|方法・メリット・事例、調査会社5選も

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
「顧客が本当に求めていることが見えない…」そんな悩みを抱える企画・マーケティング担当者の方は少なくありません。
そういった時に役立つのが、エスノグラフィーによる“現場での観察”です。
「購入に至らない理由」や「使いづらさへの違和感」など、本人すら意識していない行動の背景を丁寧に読み取ることで、定量データでは見えない本音にアプローチできます。
この記事では、エスノグラフィーの意味やメリット・デメリット、活用事例や調査会社を選ぶ際の注意点までをわかりやすく解説します。
エスノグラフィーとは?意味・やり方
エスノグラフィーの基本について解説します。
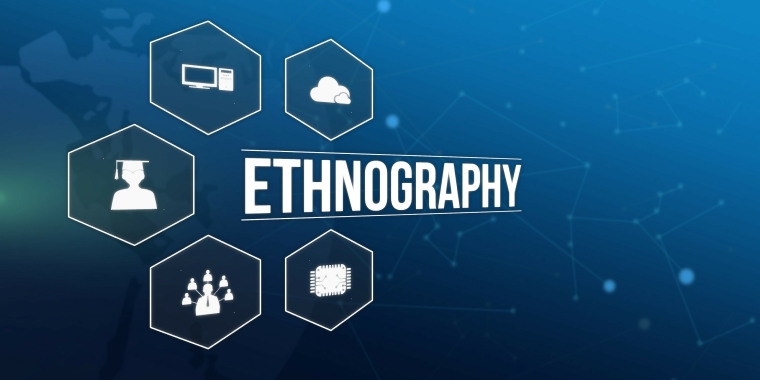
エスノグラフィーの基礎知識
エスノグラフィーとは、顧客の無意識的な行動や習慣、言葉にならない不満や期待など、アンケートや数値分析(=定量データ)では捉えきれない「顧客のリアル」を明らかにする、定性調査(質的調査)の一つです。
「どうしてその商品を選んだのか?」という問いに対して、顧客が自覚していない感情や場面の影響があることは数多くあります。エスノグラフィーでは、こうした行動の背景にある文脈や理由を、現場での観察や参与によって丁寧に拾い上げていきます。
エスノグラフィーによって得られた気づきは、製品の改良や新たなニーズの発見に直結する貴重なインサイトとなり、経営や戦略に生かすことが可能です。
マーケティングリサーチにおけるエスノグラフィの位置づけと役割
マーケティングリサーチとは、企業や組織が顧客や市場の実態を把握し、より良い意思決定を行うために実施する「情報収集と分析のプロセス」全体を指します。調査手法は、目的に応じて、定量調査と定性調査の2つに大別されます。
エスノグラフィーは、マーケティングリサーチにおいて、特に「ユーザーの本当の姿」や「潜在的なニーズ」を深く掘り下げるために使われる定性調査の一つです。アンケートや統計データなどの定量調査が、市場全体の傾向や顕在化したニーズを把握するのに対し、エスノグラフィーは現場観察を通じて、ユーザー自身も意識していない行動の背景や価値観を理解することを目的としています。
エスノグラフィーの調査方法|5ステップ
エスノグラフィー調査は、闇雲に実施しても成果は得られません。調査目的の明確化から観察、分析までを体系的に進めることが成功の鍵です。ここでは、エスノグラフィーの調査における基本的な5ステップを紹介します。
1. 調査設計
まずは「何を明らかにしたいのか」という調査の目的を明確にします。その目的に沿って、課題や仮説を整理し、どのような情報を得たいのかを設計することで、調査の方向性がぶれにくくなります。
2. 対象者とフィールドを設定
次に、調査対象者をリクルートし、観察を行うフィールド(生活環境や場面)を決定します。ユーザーの行動を最も自然な形で観察できる場所を選定することが重要です。調査目的に合ったフィールドを設定することで、よりリアルな行動を観察できます。
3. 観察の実施
設定したフィールドで、対象者の行動や発言を観察し、できるだけ自然な状態で記録します。観察によって対象者の行動を変えてしまわないよう、観察者は介入を最小限にとどめ、対象者が普段どおりに過ごせる環境を維持します。
4. データ収集・整理
観察によって得られた情報は、写真・動画・音声・メモなどを用いて記録します。行動そのものだけでなく、時間帯・場所・人間関係・環境変化といった文脈情報もあわせて残すことが重要です。収集したデータは、後の分析に活かしやすいように、時系列や場面ごとに整理・分類しておきます。
5. 分析
整理したデータをもとに、行動パターンや共通点を分析します。観察した事実と、インタビューなどで得た言葉を突き合わせることで、「なぜその行動をとったのか」という深層的な動機や価値観を明らかにします。得られた知見(インサイト)は、新たな商品開発やUI/UX改善、ブランド戦略の方向性を導く重要な基礎データとなります。
注目されるハイブリッド型エスノグラフィー
近年では、従来のエスノグラフィーに定量的なデータ分析を組み合わせる「ハイブリッド型エスノグラフィー」が注目されています。たとえば、対面での行動観察とアンケート調査を組み合わせる方法や、事前にテスト製品を対象者の自宅へ送付して生活の変化を記録してもらう形式などです。
質的データによる深い理解に、定量データの広い視点を掛け合わせることで、より本質的な課題発見や意思決定の精度向上につながると期待されています。
エスノグラフィー調査のメリットとデメリット

エスノグラフィーは、ユーザー理解を深めるうえで非常に有効な手法ですが、決して万能ではありません。ここでは、ビジネスで活用する際に知っておきたい主なメリットとデメリットを整理します。
メリット|潜在ニーズを発見できる5つの理由
エスノグラフィー調査の主なメリットは次のとおりです。
- 顧客自身が気づいていない、無意識の行動を発見できる
- 表面化していないニーズや不満にアプローチできる
- 定量調査では得られない、行動の背景を深く理解できる
- 商品・サービス改善のヒントが現場から直接得られる
- 顧客視点の施策立案が可能になり、施策のズレを減らせる
エスノグラフィーの最大の強みは、言語化されていない「潜在ニーズ」や「心理的ハードル」を行動から読み取れる点にあります。これにより、表面的な要因にとどまらず、本質的な顧客課題の発見や新たな価値提案につなげることができます。
デメリット|実務で起こりやすい5つの落とし穴
エスノグラフィーは深い洞察を得られる一方で、実務での運用にはいくつかの注意点や課題もあります。主なデメリットは以下のとおりです。
- 観察者の主観が入りやすく、バイアスがかかる可能性がある
- 調査対象者の数が少なく、全体傾向の把握には向かない
- 実施に時間と手間がかかり、人的リソースを必要とする
- 分析・解釈に専門性が求められ、再現性に課題が残る
- 得られたデータが曖昧になりやすく、意思決定に結びつけづらいことがある
エスノグラフィーのデメリットは、調査結果が観察者の主観に影響されやすく、信頼性や客観性の担保が難しい点にあります。調査者がフィールドで何に「注目」し、どう「解釈」するかが個人の経験や思い込みに大きく左右されるからです。
このリスクを避けるには、まず調査設計の段階で「何を明らかにする観察なのか」を明確化し、複数名で観察視点を共有することが重要です。さらに、アンケートやセンサーデータなどの定量情報を組み合わせるハイブリッド型エスノグラフィーを導入することで、主観的な偏りを抑え、より客観的で再現性の高い分析が可能になります。
ビジネスでのエスノグラフィー活用事例
ビジネスの現場では、エスノグラフィーがさまざまな分野で活用されています。ここでは、活用事例を紹介します。
一般的な活用事例一覧
エスノグラフィーの代表的な活用事例をまとめました。
| 活用領域 | 具体的な活用方法 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 商品・サービス開発 | ユーザー宅での製品利用状況を観察し、改良ポイントを発見 | 隠れたニーズを把握し、新製品のヒントに繋がる |
| UI/UXデザイン | アプリ使用時の行動や躊躇の瞬間を記録 | 直感的でストレスのない導線設計が可能になる |
| 店舗運営 | 店内動線や顧客の動きを観察し、売り場を改善 | 回遊率・購買率の向上に貢献 |
| 人事・組織開発 | 職場での社員の動きや会話を記録し、課題を発見 | 業務プロセスの改善やエンゲージメント向上に活用 |
| ブランディング・広告 | 顧客のライフスタイルや価値観を観察し、言語化 | 共感を得る広告コピーやストーリーテリングの素材になる |
エスノグラフィーは、生活者や従業員の無意識の行動や感情を読み解くことで、企画や経営判断の質を高める調査手法です。商品開発から組織改革、広告制作まで幅広く活用されており、得られたインサイトをもとに潜在ニーズの発見やサービス改善、ブランド価値の向上につなげることができます。
具体的な企業事例2選
エスノグラフィーを実際に取り入れた企業の事例を紹介します。具体的な活用シーンを知ることで、導入後のイメージや効果をより明確に掴むことができます。
コンビニPB商品の改善事例
ある大手コンビニチェーンでは、プライベートブランド(PB)商品の差別化を目的に、エスノグラフィー調査を実施しました。ファンユーザーの自宅を訪問し、実際の利用シーンを観察する調査を行い、その結果をもとに開発担当者を交えたワークショップを開催しています。
従来の数値データでは見えなかった生活動線や使用状況、そしてユーザー自身も気づいていなかった選択理由や心理的ハードルが明らかになり、商品の改良方針や新しい開発テーマの立案に活かされています。
キッチン観察からの製品開発事例
ある製品開発支援企業では、「キッチン空間」に着目し、エスノグラフィー調査を行いました。対象者の家庭を訪問し、調理行動、道具の配置、清掃・衛生意識などの行動を観察する手法を用いて、生活の中に潜むニーズを抽出しています。
その後、観察結果をもとにワークショップを開催し、チーム全体で顧客理解を共有しました。さらに、深層インタビューにより改良点を掘り下げ、それらを製品企画に反映させています。
エスノグラフィー調査会社の選び方|押さえておきたい4つの注意点
エスノグラフィー調査を成功させるには、パートナーとなる調査会社の選定が非常に重要です。ここでは、依頼前に確認しておきたい4つのチェックポイントを紹介します。
調査目的に応じた専門性を持っているか確認する
まずは、自社の業界やテーマに精通しているかを確認します。専門性の高い会社ほど、得られるインサイトの深さや質も高まる傾向にあります。
ただし、「エスノグラフィー対応」と記載があっても汎用調査に近いケースがあるため注意が必要です。商品開発、UX改善、組織改革など、自社の目的に近い領域での実績があるかを、具体的に確認することが大切です。
対象者リクルートの実績と難易度対応力があるか
「誰を観察するか」が調査の質を大きく左右するため、対象者選定の精度やネットワークの広さは重要な判断基準です。地方在住者や高齢層など、対象者がニッチになるほどリクルートの難易度は上がるため、過去に同様の条件で調査を実施した実績があるかを確認しておくと安心です。
観察手法・記録・分析のフローが明確かどうか
エスノグラフィーでは、観察から記録、分析までのフローが明確であることが重要です。フローが不明瞭な場合、重要な行動データを見落としたり、調査結果が単なる発言や事実の羅列になってしまったりするリスクがあります。打ち合わせ時に、「どのように観察・記録し、どんな形式で報告されるのか」を具体的に確認しておくと安心です。
自社との連携体制に安心感があるか
調査会社を選ぶ際は、「自社の目的にどこまで共感し、伴走してくれるのか」「最終的にどのレベルのアウトプットを期待できるのか」といった連携体制の安心感も欠かせません。
特に初めてエスノグラフィー調査を発注する場合は、調査設計のひな形やサンプルレポートを取り寄せ、複数社を比較検討することをおすすめします。あらかじめ自社に合った調査スタイルや分析力を把握しておくことで、調査会社選びの失敗を防ぎ、安心してプロジェクトを進めることができます。
エスノグラフィー調査におすすめの調査会社5選
| 企業名 | サービス内容 | この会社の優位性 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ネオマーケティング | 訪問観察調査で生活者の潜在ニーズを探索。新商品開発支援にも強み | 2,889万人の大規模パネルと4万件超実績。独自のインサイトドリブン®で本質的な顧客理解 | 新商品開発や既存商品改善で生活者の潜在ニーズや本音を深く理解したい企業 |
| 日本インフォメーション株式会社 | メーカー企業を中心に様々なマーケティングリサーチを実施する総合リサーチエージェンシー | 「デプスインタビュー」「日記」「観察」などの手法を組み合わせる多角的なリサーチ手法を持つ | 顧客理解、ユーザーインサイトの深堀を必要とする企業 |
| 株式会社電通マクロミルインサイト | フィールドワーク+生活文脈の深掘り。生活者インサイトからコンセプト開発まで一貫支援。 | 生活者理解に特化した専門チームと、膨大なマクロミルデータとの連携が強み。 | 商品開発やブランディングを検討中のマーケティング部門 |
| 株式会社アスマーク | 訪問型の行動観察に強み。20年以上のノウハウによる高精度リクルート対応。 | 地方や高齢層など、リクルートが難しい対象への実施経験が豊富。 | 高齢者や介護など、特定生活環境に注目した調査を行いたい企業 |
| 株式会社プラグ | デザイン会社と調査会社が合併してできた会社。消費財パッケージ開発が強み。 | パッケージデザイン評価専門調査サービスがある。 | 商品開発やブランド戦略に課題を抱える企業、一貫したサポートを求める企業 |
エスノグラフィー調査といっても、各社の得意領域や対象者へのアプローチ手法は大きく異なります。生活者の行動全体をじっくり観察するのか、それとも特定の行動プロセスに絞って仮説検証を行うのかによって、適した調査会社や設計手法は変わります。
自社の課題に合ったパートナーを選ぶことが、表面的なデータではなく行動の「なぜ?」まで深掘りできるインサイトを得るための第一歩です。ここでは、代表的なエスノグラフィー調査会社を紹介します。
株式会社ネオマーケティング|顧客理解から商品・サービス開発まで支援

参照元: 株式会社ネオマーケティング
ネオマーケティングは、市場調査、コミュニケーション戦略、カスタマーサポートまでワンストップで提供する総合マーケティング支援会社です。
2,889万人超の大規模パネルと累計40,000件以上の豊富なプロジェクト実績を持ち、デザイン思考をマーケティングに取り入れた独自の商品・サービス開発手法「インサイトドリブン®」で、生活者のインサイト創造から、商品開発、プロモーション支援、PDCAの実行までサポートします。
日本インフォメーション株式会社|経験豊富なリサーチのプロが多数在籍

参照元: 日本インフォメーション株式会社
日本インフォメーションは幅広いジャンルの調査に対応できる人材と体制を持っており、自社の課題が見えていない企業の相談先として最適な調査会社です。
ただのデータ提供ではなく意思決定に役立つConsumer insightsの提供を心掛け、経験豊富なリサーチャーによる普遍的なリサーチのノウハウと、最新のIT技術を掛け合わせ、付加価値の高いリサーチを提供します。
相談先に迷った際には、心強い選択肢となるでしょう。
株式会社電通マクロミルインサイト|生活者視点を深掘りしたいならここ

参照元: 株式会社電通マクロミルインサイト
電通マクロミルインサイトは、生活者の行動や意識を深く掘り下げるフィールドワーク型のエスノグラフィー調査に強みを持つ企業です。
現場に入り込んで観察し、生活者の言動や感情の背景にある“文脈”を丁寧に読み解くことで、単なる表層的なニーズではなく、その人の価値観やライフスタイルの全体像を把握することができます。特に同社は「生活文脈を起点としたコンセプト開発」に強みを持っています。この強みは商品やサービスを「企業側の理屈」ではなく、「ユーザーの暮らしの中に自然に入り込めるか」という視点から設計することを意味します。
「忙しい朝に使いやすい家電とは?」「共働き家庭に響く広告メッセージとは?」といった、日常のリアルな状況を起点にアイデアを練り、コンセプトを設計することで、より共感されやすく、支持されるブランドづくりにつながります。
「生活者の気持ちや行動の背景ごとに読み解いて、ブランドの芯をつくりたい」そんなマーケティング担当者や、ブランドの世界観設計に取り組むクリエイティブチームにとっては、まさに“戦略的な伴走者”となる一社です。
株式会社アスマーク|現場密着型の「行動観察」に強みあり

参照元: 株式会社アスマーク
アスマークは、現場観察型のエスノグラフィ調査を得意とする調査会社です。
現場に足を運ぶことで、実際の生活状況や業務環境に即した“行動の文脈”を正確に把握できるため、机上の仮説では気づけない不便や感情の機微を発見できるという利点があります。
自宅訪問や職場同行などを通じ、生活者の無意識な行動や、習慣に埋もれた不便を可視化することに長けています。特に、「高齢者の在宅介護」「収納行動」「キッチン動線」といった日常のルーティンが課題の核心になるような領域において、観察ベースで本質的な気づきを導く調査実績が豊富です。
リクルートの難しい対象者にもアプローチできるネットワークと、丁寧な事前調整・きめ細かな現場対応力も魅力のひとつ。対象者と信頼関係を築く力があるため、より自然でリアルな行動データが取得できるのも強みです。「とにかく現場を見たい」「生活者のリアルをとらえたい」と考える企業にはうってつけです。特に、商品設計やUI設計に“暮らしの視点”を持ち込みたいチームにおすすめできます。
株式会社プラグ
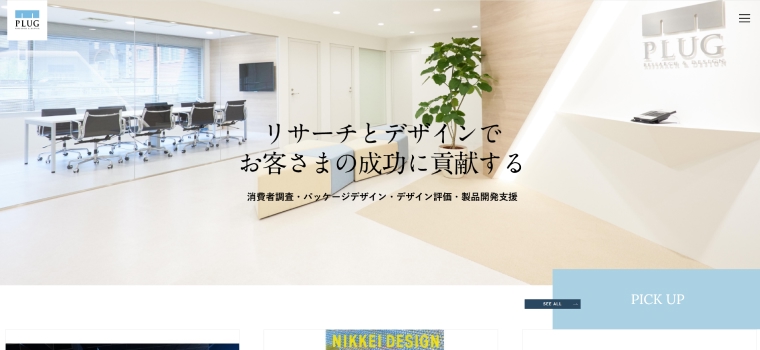
参照元: 株式会社プラグ
プラグは、デザイン会社と調査会社が合併してできた会社です。特に、消費財パッケージ開発が強みであり、パッケージデザイン評価専門調査サービスがあるのが特徴です。
100万人規模のインターネットモニター会員を有し、オンライン調査システムの充実度にも定評があります。また、「製品開発支援」の一環として、キッチンでのユーザーの行動を観察した実績もあります。
商品開発やブランド戦略に課題を抱える企業、あるいはリサーチからプロモーションまで一貫したサポートを求める企業に特におすすめです。
エスノグラフィー調査で「気づき」をビジネス成果へつなげる
この記事では、エスノグラフィー調査の基本から活用事例、おすすめの調査企業までを詳しく紹介しました。
エスノグラフィーは、観察と参与を通じて生活者のリアルを捉える質的調査手法です。顧客の無意識な行動や、言葉にならない不満や期待を把握するのに特に有効であり、商品開発やUX改善、店舗運営、人事・組織開発、広告制作など、幅広い分野で活用されています。
一方で、得られるインサイトは深いものの、調査者の主観やバイアスが入りやすいというリスクもあります。そのため、調査会社を選ぶ際には、専門性やリクルート力、連携体制といったポイントをしっかりと見極めることが重要です。
自社の目的や課題を整理しながら、最適な調査パートナーを選定し、ユーザー理解を競争力に変える第一歩を踏み出してください。
リサーチ会社探しにお困りなら
調査会社マッチング
貴社の課題をヒアリングし、課題解決に最適なリサーチや調査会社をご紹介するサービスです。
調査会社選びにお困りなら是非ご相談ください。



