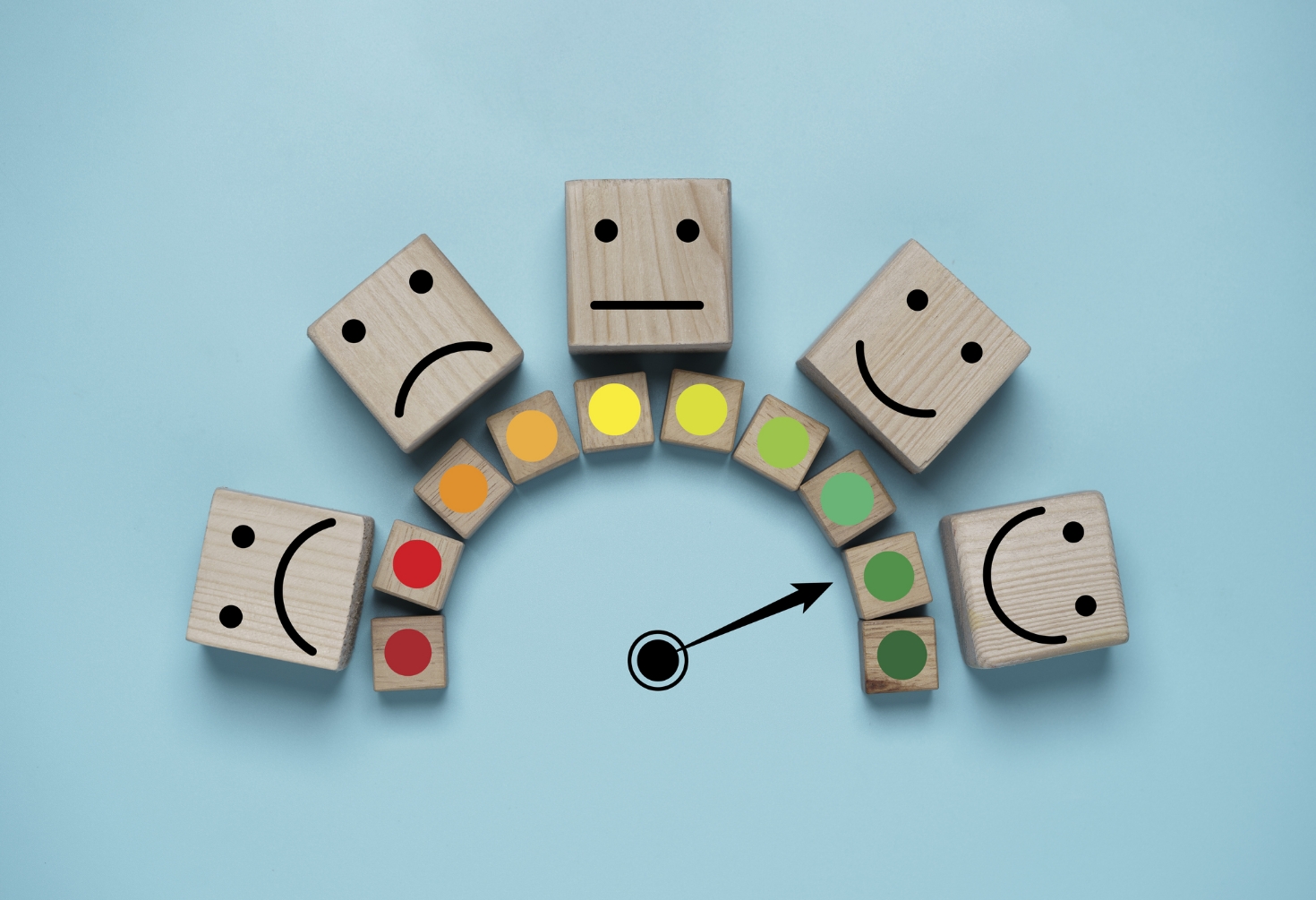アンケート設計・集計のやり方と注意点|大手アンケート会社10社の比較と失敗しない選び方のコツ

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
「アンケートを取ったのに、どう活用していいか分からない…」 そんなお悩みをお持ちではありませんか?
せっかく時間と手間をかけて集めたデータも、うまく読み解けなければ宝の持ち腐れです。
どの設問が本質を捉えていたのか、集計はどう整理すべきか、分析の視点は合っているのか……など。
設問設計や集計方法、分析の視点次第で、データは単なる数字にも、次の一手を導く“判断材料”にもなります。自社にとって本当に意味のあるアンケートにするには、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要があります。
この記事では、アンケート調査と集計の基本から、活用するための実践的な考え方について詳しく解説しています。
アンケート設計や集計・分析の委託先をお探しの方はこちらをご覧ください。
アンケート設計・集計・分析が得意な調査会社10社を比較
アンケート集計の基本とは?意思決定を支える正しいデータ活用の第一歩

- 意思決定に必要な情報を得られるよう、目的に沿った設問設計を行う
- ローデータに誤入力や欠損がないかを集計前にチェックし整備しておく
- どの属性で切り分けて分析するか、視点を明確にしておく
- 「満足」や「利用経験」などの定義・指標は社内で統一しておく
- グラフや表を使って直感的に伝わるように可視化を工夫する
アンケート集計の目的は、「現状の課題や顧客の本音を把握し、次の意思決定に活かすこと」であり、単に数字を並べることではありません。集めた声の「意味」を、文脈や背景とあわせて丁寧に読み解き、有効なアクションプランへとつなげる“判断材料”へ変換するのがアンケート集計と分析の本質です。
特に重要なのは、「誰が」「なぜ」その回答をしたのかという意図を、年齢や役職、利用経験といった属性や行動傾向と照らし合わせながら掘り下げることです。そのためには、事前に「どのような判断に役立てたいか」という設問設計の意図を明確にしておく必要があります。
また、アンケートの集計後は、数値の羅列にとどまらず、意味のある切り口で分析視点を定めることが不可欠です。
アンケート集計は、単なる報告資料を作るための作業ではありません。経営や戦略の舵を切るための「論理的根拠」となり、社内や意思決定者を納得させるための説得力ある武器になります。同じデータでも、扱い方ひとつで導かれる結論は180度変わることもあります。
「まず何を明らかにしたいのか」を最初に明確にし、その目的に沿って集計と分析を丁寧に行うことが、成果につながる第一歩です。
アンケート集計の重要性は?アンケートを集めた後の活用の意義
アンケート活用時の4つのチェックポイント
- 単なる「集計作業」で終わらせず、次のアクション設計までを意識する
- 自由記述は「数字に現れない生の声」として分析する
- 属性別や条件別に切り分け、偏った読み取りにならないように注意する
- 数値だけで説明せず、関係者に「伝わる」形で示唆や提案まで落とし込む
アンケートは、集めることがゴールではありません。本当に意味があるのは「集めた後にどう使うか」です。
例えば、商品改善のためにアンケートを取ったとします。その結果、「満足度がやや低下している」とわかっても、理由を読み解けなければ何も変わりません。だからこそ、必要になるのが、集計と分析です。
「どの年代の満足度が落ちたのか」「どの機能に対する不満が強いのか」といったように、回答結果を属性別や設問別に細かく切り分けて分析することで、施策につながる示唆が見えてきます。
また、数値データだけでは拾いきれない“生の声”が、自由記述の中には多く含まれています。
「最近、問い合わせ対応に時間がかかるようになった」などのユーザーからのコメントは、設問にはない実務上の課題を浮き彫りにしてくれます。こうした記述は、数値に裏打ちされた分析をより立体的にし、施策の納得感を高めるヒントになります。
新商品の投入判断やサービス改善の方向性、組織マネジメントの調整など、社内のさまざまな施策判断を支える裏付け材料になります。
アンケート調査の外部委託は本当に有効?メリットとデメリットを徹底比較
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 専門性 | 設計・回収・分析までプロの視点で対応してくれる | 調査内容を正しく伝えないと、目的から逸れたアウトプットになる |
| 工数削減 | 社内リソースを使わずに調査業務を任せられる | コミュニケーションに時間がかかる場合もある |
| スピード | 短納期でも対応可能な調査会社が多い | 確認や修正に追われると、かえって遅くなることも |
| 客観性 | 外部の視点で分析されるため、バイアスが少ない | 社内の事情や背景を汲みにくいことがある |
| 品質 | レポートやデータ形式が整っており、説得力がある | 希望と異なる形式になることもある。事前の共有が必須 |
アンケート調査を外部に委託する最大の魅力は、「プロの手で、効率よく、質の高いアウトプットが得られること」です。専門家のノウハウを借りることで、設問設計の精度や分析の深さが格段に向上し、社内での説得力も高まります。
ただし、アンケート調査を行う際に「調査の目的や実施したい背景がうまく伝わっておらず、期待していた視点とは異なる結果になってしまった」など、アウトプットの齟齬が起こるリスクも少なくありません。
また、アンケート内容の修正対応や集計作業に追加費用が発生するケースもあるため、事前のすり合わせや見積確認が非常に重要です。
アンケート調査会社をうまく活用すれば、外部委託は社内の限られたリソースで調査を成功させる強力な手段となります。
有意義な集計・分析のために必要なアンケート設計のポイント

| 準備項目 | 内容 |
|---|---|
| 設問設計 | 調査目的に沿った問いを設定し、回答者が迷わない表現にする |
| 回答形式の選定 | 選択式・自由記述・数値入力など、集計後の活用を想定して選ぶ |
| サンプル設計 | 対象者の属性(年齢・性別・役職など)を適切に分布させる |
| 集計軸の設定 | どの切り口で分析するか(例:性別×年代)をあらかじめ決めておく |
| バイアス対策 | 誘導的な質問や偏った選択肢にならないようチェックを行う |
アンケートは、質問の内容・順番・言い回しが回答者の心理や解釈に影響を与えてしまい、信頼性の低いデータになってしまうリスクがあるため、事前の設計が重要です。
中でもまず注意すべきなのは、設問に潜む“バイアス(偏り)”のリスクです。
「このサービスに満足していますか?」という表現は、無意識に“満足している前提”を与えるため、肯定的な回答を誘導しやすくなります。これは「誘導バイアス」と呼ばれ、設問の構成次第で集計結果が歪んでしまう典型例です。
適切なアンケート設計を行うには、「中立的で選択肢に偏りがない表現」に配慮し、「回答者が自由に意見を表明できる空間」を作ることが欠かせません。アンケート結果を信頼できるものにするには、設計時にどれだけバイアスを抑え込めるかがカギになります。
また調査方法によっても結果の傾向は変わります。
アンケートの調査方法で解答はどのように変わるのか?
| 調査方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| Webアンケート | オンライン上で回答を収集 | スピードとコストに優れる | 高齢層の回収率が低い傾向 | 短期間で多数の回答を得たいとき |
| 郵送アンケート | 紙で郵送・返送される形式 | 高齢者層にも届きやすい | 回収まで時間がかかる | じっくり考えた回答を集めたいとき |
| 面接調査 | 調査員が対面で実施 | 深掘りした定性情報が得られる | コストと手間が大きい | 複雑な内容や重要意思決定前の調査 |
| 電話調査 | 電話越しに口頭で聴取 | 短時間でリアルタイムな反応を得られる | 長文回答には向かない | 緊急性が高く、短く済ませたいとき |
| 会場調査(CLT) | 会場に集めて一斉に回答 | 商品体験後の即時フィードバックが可能 | 対象者の集客が大変 | 試作品・パッケージ評価など体験型調査 |
アンケートの方法によって、得られるデータの「質」や「傾向」は大きく変わります。
上記の表のようにWebアンケートは、スピーディーかつ低コストで実施できる反面、高齢者層などデジタルに慣れていない層からの回答が得にくい傾向があります。
一方で、郵送アンケートは回収に時間がかかりますが、紙媒体に慣れた世代から丁寧な回答が集まりやすくなります。
また、面接調査や会場調査のように「顔を合わせて回答を集める」形式では、非言語の反応や深掘りした意見も得られる点で優れています。
アンケートを行う前に押さえておきたい5つの準備ポイント
アンケート準備のチェックリスト
- 調査目的を明確にして、何を知りたいのかを言語化しておく
- ターゲット(対象者)の条件を具体的に設定する
- 設問数は15~20問程度に絞り、回答負荷を抑える
- 回答形式(選択式/自由記述など)を目的に応じて選定する
- 社内での共有や分析を見据え、あらかじめ集計軸を想定しておく
アンケート調査の成功は、実施前の「設計の質」にかかっています。
その中でも特に重要なのは、「目的」と「対象」と「聞き方」の3点です。
商品改善のヒントを得たいのに、単なる満足度ばかりを尋ねてしまっては、本質的な改善にはつながりません。また、アンケートの対象者選定が曖昧だと、得られる結果もブレてしまいます。
まずは調査のゴールを社内で共有し、設問ごとに「この質問は何の意思決定に使うのか」を確認するようにしましょう。加えて、アンケートの回答者が途中で離脱しないよう、設問数は少なめに、回答形式はシンプルに整えるのがポイントです。
こうした工夫を積み重ねることで、集計後の分析もしやすくなり、次の一手につながる“使えるデータ”が手に入ります。
もし、自社にアンケート設計や分析のノウハウが十分でないと感じたら、外部の専門家に委託するのもひとつの手です。
アンケート設計・集計・分析が得意な調査会社10社を比較
| 会社名 | サービス内容 | この会社の強み | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| マイボイスコム | コンサル型リサーチで、ネット/オフライン多様な調査手法を提供 | 120万人にリーチできるパネル活用と徹底した品質管理、専門リサーチャーが調査をトータルサポート | 信頼できるデータで専門的課題を解決したい企業、大学・研究機関の方 |
| 日本リサーチセンター | オンライン調査からオフライン調査まで幅広い調査手法に対応 | 訪問・郵送・CLTなどのオフライン調査と、Webモニターのオンライン調査と両方に対応 | 調査対象の幅が広く、様々な条件を相談したい方 |
| 市場開発研究所 | 品質重視のインターネットリサーチを提供。企画・実施・集計・分析が可能。 | 経験豊富な専属リサーチャーが、迅速・高精度な調査を一貫支援 | 迅速かつ質の高いリサーチと、多角的なコンサルを求める方 |
| Quest Research | AIでアンケート調査の集計・分析、レポート作成、インタビュー、海外調査を支援 | AI活用で高速・高品質なリサーチを実現。自動インタビューや海外調査にも対応 | 高速で定量・定性調査や海外調査を希望する企業 |
| フォリウム | リサーチのプランニングから実査、レポート作成まで、マーケティングプロセス全体を支援 | 験豊富な人材による、高品質でスピーディなアウトソーシング体制が強み | ストを抑えつつ、高品質な調査運用を実現したい企業 |
| 日本インフォメーション | メーカー企業を中心に様々なマーケティングリサーチを実施する総合リサーチエージェンシー | 長年の実績を有するスタッフが、専任リサーチャーとして最適な手法を提案 | 自社に専門知識を有する人材がいないため、ワンストップでリサーチを任せたい方 |
| マクロミル | オンラインアンケートを中心に、マーケティングやコンサルなどのサービスを提供 | 業界トップクラスの調査実績と高品質なアンケートサービス | データ分析から戦略立案までサポートしてほしい方 |
| クロス・マーケティング | Webリサーチを中心に多様な市場調査手法を提供 | 大規模調査から、出現率の低いターゲットへの調査まで柔軟に対応できる | 調査の開始からデータ活用まで伴走しながら支援をしてほしい方 |
| サーベイリサーチセンター | 全国の様々な民間企業から、官公庁・自治体等まであらゆるリサーチ業務に対応 | 各分野のスペシャリストによるリサーチソリューションの提供により様々な調査テーマに対応 | 細かい要望にも対応してくれる調査会社を望む方 |
| トリム | 紙・Web対応、集計・レポート作成、自由記述の分析まで一貫 | 柔軟な対応力とスピード。紙媒体にも強く、手厚いサポート | 過去の紙アンケートを活用したい/細かい要望を伝えたい方 |
アンケート調査を外部に委託する際、選ぶ会社によって得られる「データの質」と「活用のしやすさ」が大きく変わるのは、各社が提供するサービス範囲・対応力・分析ノウハウに差があるからです。
アンケートで仮に同じ設問を使っても、対象者の抽出精度やデータのクリーニング方法、レポートの深度が異なれば、結果の信頼性や示唆の引き出し方に大きな違いが生まれます。
アンケート調査や集計の「目的」「規模」「体制」によって選ぶべき会社が変わるため、自社の状況に応じた比較検討が欠かせません。
この章では、主要なアンケート調査会社10社のサービス内容・優位性・適した用途を分かりやすく比較しています。
マイボイスコム|リサーチャーによるコンサル型リサーチで、多様な調査手法を提供

参照元: マイボイスコム株式会社
マイボイスコムは、1999年設立の伊藤忠グループのリサーチ会社です。
「コンサル型リサーチ」を強みとし、専門のリサーチャーがアンケート調査設計からデータ回収、集計、分析、レポート作成までを一貫してサポートします。
約120万人の大規模パネルと約28項目の詳細属性、徹底した品質管理(不正回答対策、多頻度回答防止、厳密なデータクリーニング等)により、信頼性の高いアンケートデータを提供。インターネット調査を中心に、会場調査などのオフライン調査にも対応し、BtoCだけでなく、大学・研究機関の複雑な学術調査にも豊富な実績を持ちます。
信頼できるデータで事業課題を解決したい企業や、学術的・専門的な複雑な調査を依頼したい企業におすすめです。
日本リサーチセンター|オンライン・オフラインどちらの調査もできる対応力

参照元: 株式会社 日本リサーチセンター
日本リサーチセンターは幅広い調査方法とノウハウを有しており、複数の調査対象を抱える企業には最適の調査会社。
企業の市場戦略にかかせない市場調査、世論調査、海外調査など、マーケットを包括的な視点でとらえ、全方位にわたり事業戦略を支援してくれます。
自社で調査が困難な課題の相談先として、心強い選択肢となるでしょう。
株式会社市場開発研究所

参照元: 株式会社市場開発研究所
市場開発研究所は、品質を重視したインターネットリサーチを専門に提供しており、長年のマーケティングリサーチ経験と実績に基づいた高品質なサービスを展開しています。最大の特徴は「営業窓口=リサーチャー」という専属サポート体制です。経験豊富なリサーチャーが調査設計からレポート作成までを一貫して担当し、調査目的や背景を深く理解した上で、より精度の高い調査を実現します。
豊富な実績で培ったノウハウを活かした高精度な集計を提供し、クロス集計や多変量解析(因子分析、クラスター分析、コレスポンデンス分析など)、自由回答のアフターコード集計にも対応しています。インターネット調査に留まらず、郵送調査、会場集合調査、グループインタビューといった多様な調査手法との連携も可能であり、目的に応じた最適なリサーチ提案が強みです。
株式会社Quest Research

参照元: 株式会社Quest Research
Quest Researchは、AIを活用した高速・高品質なリサーチを得意とする調査会社です。経験豊富なリサーチャーが調査設計からレポート作成まで一貫して伴走サポートし、お客様から見える部分・見えない部分を問わず徹底的に効率化することで、圧倒的なスピードを実現しています。
アンケート調査を最短1営業日で実施可能で、集計・分析も最短2週間で完了できます。AIが示唆出しをサポートし、パワーポイント形式でレポート出力が可能で、分析から資料作成までをスピーディーかつ高品質に実現します。
フォリウム
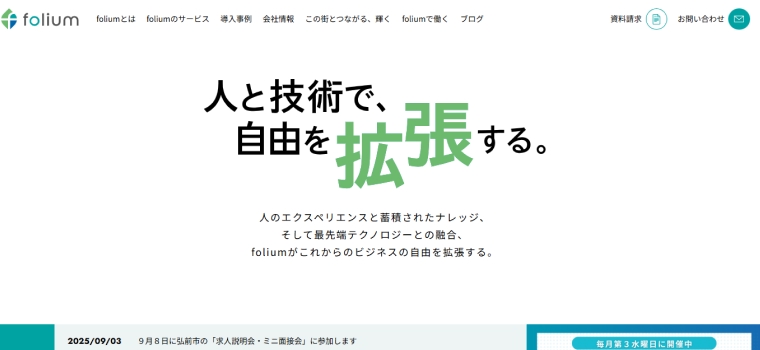
参照元: 株式会社フォリウム
フォリウムは、インターネットリサーチ業務のアウトソーシングに特化したリーディングカンパニーです。調査のプランニングから実査、レポート作成まで、マーケティングプロセス全体を支援する「マーケティングプロセスオーグメンテーション」を提供しています。
業務習熟度が高く経験豊富な人材が、高品質でスピーディな調査運用体制を実現しています。リサーチ業務の属人化やリソース不足といった課題を解決し、コストを抑えながらスピーディーな事業拡張をサポートします
日本インフォメーション株式会社|経験豊富なリサーチのプロが多数在籍

参照元:日本インフォメーション株式会社
日本インフォメーション株式会社は幅広いジャンルの調査に対応できる人材と体制を持っており、自社の課題が見えていない企業の相談先として最適な調査会社です。
ただのデータ提供ではなく意思決定に役立つConsumer insightsの提供を心掛け、経験豊富なリサーチャーによる普遍的なリサーチのノウハウと、最新のIT技術を掛け合わせ、付加価値の高いリサーチを提供します。
相談先に迷った際には、心強い選択肢となるでしょう。
マクロミル

参照元: 株式会社マクロミル
株式会社マクロミルは、オンラインリサーチを主軸に、インターネット調査やデジタルマーケティング、データコンサルティングなど多彩なサービスを展開している企業です。
業界トップクラスの調査実績と高品質なアンケートサービスを誇り、柔軟なシステムで多様なマーケティング課題に対応しています。国内外のネットワークを活かし、データ分析から戦略立案まで、企業の意思決定を支えるサポートを行っています。
クロス・マーケティング

参照元: 株式会社クロス・マーケティング
株式会社クロス・マーケティングは、課題や目的に応じてWebリサーチを中心に、定性・定量の多様な市場調査手法を提供しています。
国内最大規模となる1,278万人超のアンケートパネルを保有し、基本属性に加えて約20のライフスタイル・購買行動カテゴリーに基づいた細かなセグメント設計ができます。
回収数の多い大規模調査から、出現率の低い条件設定の調査まで柔軟に対応できる点が強みです。海外調査や店頭での実地調査にも対応しています。
サーベイリサーチセンター|民間から官公庁まであらゆるリサーチに対応

参照元: 株式会社サーベイリサーチセンター
サーベイリサーチセンターは全国15カ所の拠点に研究員が常駐し、事務所は、独⽴した組織として各地域の調査テーマに対する対応も可能な調査会社。
経験豊富なプロジェクトマネージャーが、各分野で培ったノウハウとソリューションを複合させることで、目的に合った調査設計を提案してくれます。
初めて調査依頼される方には、心強い選択肢となるでしょう。
紙アンケートもおまかせ!柔軟対応のトリムで丁寧なアンケート集計を

参照元:株式会社トリム
トリムは、紙アンケートの集計や自由記述のテキスト分析に特化したリサーチ会社です。
これが意味するのは、デジタル化が進んでいない現場や、手元に紙資料しか残っていない状況でも、そこに眠る貴重な情報を「使えるデータ」として再活用できるということです。
トリムは「紙で配布したアンケートをまとめたい」「手書きの自由回答から傾向を読み取りたい」といったニーズに対して、アフターコーディング(自由回答を分類・数値化)や構造化された集計処理まで一貫対応できるのが大きな強みです。
報告書やプレゼン資料にそのまま活用できるデータとして納品できるため、社内共有や外部報告の手間を大幅に省けるという点で非常に実用的です。
自治体・教育機関・医療機関など、紙アンケートが主流の現場からも多く依頼されており、「手間のかかる作業をきっちりこなしてくれる安心感」が高く評価されています。
さらに、納期に対する対応力も高く、場合によっては最短で当日納品も可能というスピード感も魅力の1つでしょう。
「紙のアンケートが山積みで手が付けられない」「細かい依頼内容まできちんと聞いてくれる業者が見つからない」と悩んでいる方にとって、トリムはまさに理想的なパートナーと言えるでしょう。
アンケート調査の費用感を把握しよう|目的別・依頼内容別でざっくり理解
| 依頼タイプ | 業務範囲 | サンプル数 | 設問数 | 価格帯(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ収集のみ | アンケート配信・回収 | 1,000件 | 〜30問 | 40万円~ | 設計や分析なし |
| 設計+収集 | 調査設計・配信・回収 | 5,000〜6,000件 | 30問+スクリーニング | 200万円〜 | 全国・複数属性対象 |
| 簡易調査 | テンプレ選択・自社操作 | 100件〜 | 10問〜 | 5千円〜数万円 | セルフ型ツール |
アンケート調査にかかる費用は、「どこまで任せるか」によって大きく変わります。
データ収集のみを依頼する場合は、アンケートをモニターパネルに配信し、回収されたデータをそのまま納品してもらう形式で、相場はおよそ40万円前後です。
一方、調査設計のサポートやスクリーニング条件の設定、対象者の細かい属性指定などを加えると、調査はより高度になり、数百万円規模の費用が発生することもあります。
調査設計や集計・分析を自身で行うセルフ型のアンケートツールなら、数千円から1万円ほどで調査をスタートすることも可能です。
このように、調査の規模や目的、そして社内のリサーチ体制が整っているかどうかによって、選ぶべき価格帯や調査方法は異なります。
まずは「どのような意思決定を支えるための調査なのか」という目的を明確にしたうえで、自社にとって無理のない範囲で最適なプランを選定することが、失敗しないアンケート設計への第一歩になります。
アンケート会社を選ぶ際の5つのチェックポイント
| チェック項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 対応範囲の広さ | 設計〜配信〜回収〜集計〜レポートまで一貫して対応可能か |
| 対象者の選定精度 | 年齢・性別・エリアなど、条件設定の柔軟性と精度 |
| 実績と得意分野 | 過去に類似業界・目的での調査経験があるか |
| レポートの質 | 納品形式(PowerPoint/Excel等)や、分析の深さ・視認性 |
| 料金の明瞭さ | 見積もりが詳細で、追加費用の発生条件が明確になっているか |
アンケート会社選びでありがちな失敗は、「価格の安さ」や「知名度の高さ」だけで選んでしまい、思ったような調査結果が得られなかったというケースです。
実際には、アンケートを行う調査会社ごとに得意な調査や集計ポイント、調査領域や対応スタイルは異なり、そこが自社のニーズと合っていないと、データが活かせない“もったいない調査”になってしまいます。
社内にリサーチャーがいない場合は、調査設計やレポート作成まで一貫対応できる会社を選ぶのが安心です。過去に自社と近い業界やターゲット層での実績があるかも、安心材料のひとつになります。
そして意外に見落としがちなのが費用の内訳です。アンケートの設問数や回収数によって、委託する費用が跳ね上がるケースもあるため、「何が基本料金で、どこからが追加になるか」をきちんと説明してくれる会社を選びましょう。
このように、調査目的・社内体制・想定活用シーンを踏まえて冷静に比較することで、自社にぴったりのパートナーを見つけやすくなります。
アンケート集計・活用の基本まとめ|“数字の意味”を読み解いて施策に変える
- アンケート集計は、意思決定に必要な「判断材料」を得るために行う
- 設問設計、集計軸、バイアス対策など、調査前の準備が成果を左右する
- 数値だけでなく、自由記述の声からもヒントを得ることが重要
- アンケートの分析は属性や条件別に切り分けて、「誰が」「なぜ」そう答えたかを探る
- アンケート調査は単なる報告で終わらせず、次のアクションにつなげる設計がカギになる
アンケートは集めることが目的ではなく、課題の優先順位を明確にしたり、改善施策の方向性を導き出したりするなど、“経営やマーケティングの判断に活かす”ことに価値があります。
アンケートの調査や集計によって得られたデータをもとに「どんな行動をとるか」を決めるための材料として使うことが、本来のゴールです。
本記事では、アンケートの設計から集計・分析に至るまでの基本と注意点を丁寧に解説してきました。もし社内に設計や分析に関するリサーチノウハウが十分にないと感じた場合は、専門家の手を借りることで調査の精度と実用性がぐっと高まります。