【2026年最新】ミステリーショッパー調査会社おすすめ5社比較|相場・費用・選び方を解説【企業・店舗向け】

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
「店舗の売上が伸び悩んでいるが、原因がわからない」「スタッフの接客レベルを客観的にチェックしたい」
このようなお悩みをお持ちの店舗運営・企業担当者様にとって、顧客目線でありのままの姿を評価できる「ミステリーショッパー(覆面調査)」は非常に有効な手段です。
しかし、いざ導入しようとしても「どの調査会社に頼めばいいのか?」「費用はいくらかかるのか?」と迷ってしまうことも少なくありません。
そこで本記事では、2026年最新の費用相場と、実績豊富で信頼できるおすすめの調査会社5社を厳選して比較・紹介します。自社の課題に合ったパートナー選びの参考にしてください。
- 対象:接客改善・売上アップを目指す店舗・企業担当者
- 2026年の費用相場:15,000円〜50,000円(管理費込)/件
- おすすめ調査会社:マイボイスコム、日本インフォメーション、インパクトフィールド、MS&Consulting、クロス・マーケティング
店舗の課題が“見える化”する!ミステリーショッパーとは?

- 調査員が一般客として来店し、接客や店舗環境を評価する覆面調査手法
- 飲食・小売・サービス業など、幅広い業種で導入されている
- 調査結果は数値やコメントでフィードバックされ、現場の改善に活用できる
- 第三者視点の評価により、従業員の対応や課題が客観的に把握できる
- 調査内容・業種・目的に応じてカスタマイズが可能で、柔軟な運用が可能
「現場の接客が悪いわけではない。でも、なぜか売上やリピート率が伸びない」 そんな漠然とした違和感を抱えていませんか?ミステリーショッパーは、そうした“見えにくい課題”を浮き彫りにする調査手法です。
簡単に言えば、一般客として来店した調査員が、店舗やサービスを実際に利用し、その体験をもとに接客の質や店舗の状態を評価・報告する仕組みです。評価項目は事前にすり合わせた基準に沿っており、例えば「笑顔の有無」「清掃状況」「商品の説明力」「スムーズな誘導」など、顧客の視点で細かくチェックされます。
こうした情報が報告書としてフィードバックされることで、「何がよくて、何が足りていないか」が明確になります。
例えば「第一印象は良いが、注文後の案内が遅い」「丁寧な口調だが、専門知識に乏しい」といった、接客側目線では気づきにくい“接客のムラ”が可視化されます。その結果、スタッフ育成やマニュアル改善、サービス設計の見直しが的確に行えるようになり、結果的にCS(顧客満足度)やLTV(顧客生涯価値)の向上につながっていきます。
ミステリーショッパーは、単なる評価方法ではありません。売上や信頼を生む“接客体験の質”を、見える数字とリアルな声で照らし出す「戦略ツール」です。
“接客力”が企業の命運を分ける時代に——ミステリーショッパー導入が加速する理由
- 顧客満足度(CS)の向上が、リピート率・口コミ評価に直結する時代へ
- 店舗オペレーションの均一化が、チェーン全体のブランド維持に不可欠
- SNSやレビューサイトの普及で、接客品質の見える化が必要に
- 「現場任せ」では限界があるため、外部視点による定点観測の需要が拡大
- サービス業全般で「人手不足×教育負担」の課題が浮上し、調査結果を活かした育成が重要に
ここ数年、多くの企業が“顧客体験”に本気で取り組み始めています。その背景にあるのは、評価軸の変化です。価格や商品力だけでなく、「どんな接客を受けたか」がSNS・口コミを通じて企業価値を左右する時代になったからです。
特に飲食や小売、美容などの対面サービス業では、たった1回のクレームがレビューサイトで拡散されるリスクもあります。Googleレビューや口コミサイトの評価が0.5下がるだけで、来店数が大きく減少すると言われています。そうした中で、店舗の品質を“常に一定に保つ”ことが重要視され始めています。
しかし、接客を含む店舗の品質を現場に任せきりで安定させるのには、限界があります。そこで注目されているのが、外部の視点で「実際に何が起きているのか」をチェックできるミステリーショッパーです。
スタッフの接客にばらつきがある場合や現場の感覚では気づけないミスも、調査報告書には「案内が曖昧だった」「敬語の使い方が不安定」といった形で具体的に可視化されます。それをもとにマニュアルの見直しや育成方針を変えることで、現場全体の品質を底上げすることができます。
ミステリーショッパーは、単なる監視ではなく、企業の利益とブランド信頼を守る手段として機能します。
ミステリーショッパーの導入目的と活用法
| 業界 | 主な調査対象 | 評価ポイント | 主な活用目的 |
|---|---|---|---|
| 飲食業 | ホール接客、提供時間、料理の品質 | 笑顔・言葉遣い・料理の提供スピード | 顧客満足度向上、スタッフ教育、CS改善 |
| 小売業 | レジ対応、陳列、声かけ、売場の清潔感 | 接客態度、商品知識、店舗の清掃状況 | 購買率UP、オペレーションの均一化 |
| 金融業 | 窓口応対、相談対応、案内の分かりやすさ | 正確性、丁寧さ、信頼感のある対応 | ブランド信頼向上、苦情防止 |
| 宿泊業 | チェックイン・アウト対応、客室案内、清掃 | ホスピタリティ、スムーズな案内、設備状況 | 再来訪促進、レビュー評価の底上げ |
| 美容・クリニック | 受付、カウンセリング、施術の丁寧さ | 親しみやすさ、安心感、清潔感 | 口コミ強化、離脱率の改善 |
ミステリーショッパーは、業界ごとに「見るべきポイント」がまったく異なります。
飲食店では、料理の味やスピードだけでなく「スタッフの表情」や「アイコンタクト」が評価軸になります。一方、小売業では、売場の清潔感や陳列、レジでの対応スムーズさなど“顧客導線”が重視されます。
このように業種によって求められる接客の“正解”は変わるからこそ、それに合わせた調査設計が重要です。
ミステリーショッパーを導入する企業側のメリットとデメリット
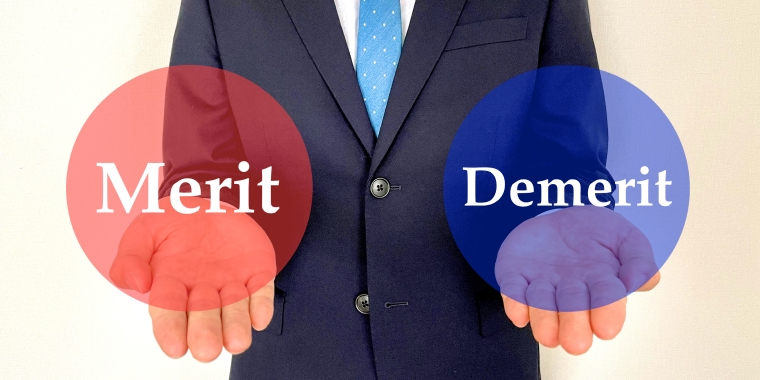
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現場の可視化 | 実際の顧客体験を通じて課題を発見できる | 一時的・局所的な評価に偏るリスクがある |
| スタッフ育成 | 具体的な改善指導に使えるフィードバックが得られる | 調査結果がスタッフのモチベーションを下げる場合がある |
| 顧客満足度の向上 | 顧客視点での接客改善につながる | 改善までに時間がかかるケースもある |
| 業務の標準化 | 複数店舗の品質を統一できる | 全店舗に一律で適用しにくい部分もある |
| ブランディング強化 | 高評価を得ればSNSや口コミで好印象が広がる | 低評価が共有されるとブランドに影響する可能性もある |
ミステリーショッパーは、顧客目線で接客やサービスの実態を“見える化”できる優れた手段です。
特に、多店舗を展開する企業にとっては、「どの店舗で、何ができていて、どこが足りないのか」を平等に測る共通のものさしとなり、サービス品質の安定化に寄与してくれます。しかし、ミステリーショッパーの活用方法を失敗してしまうと 「スタッフのやる気が下がってしまった」「調査結果をうまく活かせなかった」というトラブルが発生することも。
この章では、導入前に知っておきたいメリットとデメリット、知っておきたいミステリーショッパー実施の注意点について詳しく解説します。
サービスの安定に寄与する!ミステリーショッパーで得られる5つの価値とメリット
- 顧客目線で“現場の本音”を把握できる
- スタッフ育成に使える具体的なフィードバックが得られる
- 店舗ごとの課題や強みを可視化し、標準化につなげられる
- サービス品質の改善により、リピーター・売上UPが狙える
- 定期調査により、改善施策の成果を測定できる
ミステリーショッパーによる調査の最大の強みは、「リアルな顧客体験」を、言葉と数値で可視化できることにあります。現場のスタッフやマネージャーは日々の業務に追われており、顧客目線で接客を冷静に評価する時間も工数も持っていないからです。
例えば、調査員から「声かけのタイミングが遅れた」「案内時に説明が不足していた」といったフィードバックがあれば、それはマニュアルでは拾えない空気感のズレを表しています。このようなフィードバックは現場スタッフにとって見えにくい「不満のタネ」ですが、このタネを放置するとお客様の離脱が加速したり、口コミの低評価レビューが増えたりする可能性が高くなってしまいます。
だからこそ、ミステリーショッパーの指摘は、現場指導や研修設計の「具体的な材料」として大きな価値を持ちます。
また、複数店舗を持つ企業では、同じ基準で全店を比較できるため、接客品質のバラつきを定量的に把握できます。
ミステリーショッパーが評価するのは「個人の責任」ではなく、「店舗やスタッフ間での接客品質のばらつき」です。それを改善することで「組織全体のサービス水準を底上げし、顧客満足度やブランド信頼を安定的に向上させる」というメリットがあります。
さらに、同じ評価項目で月次や四半期ごとに継続調査を実施すれば、「初回は平均65点→3ヶ月後には78点へ改善」「“声かけ”項目の点数が上昇し、リピート率も10%向上」といった、成果が数字で見えるようになります。
「現場の体感」ではなく「事実に基づいた判断」ができるのが、ミステリーショッパー導入の最大のメリットといえます。
ミステリーショッパーの落とし穴?4つのデメリット
- スタッフが評価を意識しすぎて自然な接客が失われる恐れがある
- 報告内容が抽象的で、現場での改善に活かしづらい場合がある
- 実施コストが高く、頻度や規模によっては費用対効果が合わないこともある
- 評価結果の扱い方を誤ると、現場の信頼やモチベーションを損なうリスクがある
ミステリーショッパーは、客観的な視点でサービスの質を確認できる有効なサポートツールです。ただし、その効果はミステリーショッパーの実施方法やタイミング、調査期間や評価方法次第で大きく変わってしまいます。
例えば、一度の調査結果だけで全体を評価してしまうと、特定の時間帯やスタッフに偏った限定的な瞬間だけを切り取ってしまうリスクがあります。
季節や曜日、スタッフ構成、混雑状況はもちろん、スタッフのその日のコンディションによって現場の状態は日々変化します。そのため、単発の調査結果だけを基に現場全体を評価するのは危険です。
さらに注意したいのが、ミステリーショッパーの存在をスタッフが意識しすぎたときの反応です。
「誰が見ているかわからない」と構えた現場では、過剰なマニュアル対応や不自然な笑顔が増えることがあります。その結果、いつもの良さや自然な接客の流れが崩れ、本来のサービススタイルからかけ離れてしまうことも。
こうした状態が続くと、調査結果が“本来の接客の質”を正確に反映しなくなります。その結果をもとに改善施策を講じても現場には浸透せず、「ミステリーショッパーを実施したけど変化が感じられない」というギャップに繋がってしまいます。
そういった事態を避けるためにも調査目的や評価基準を現場と共有し、改善の意図を丁寧に伝えたうえで、フィードバックとフォローアップをセットで行うことをおすすめします。
ミステリーショッパー導入で注意したいスタッフへの影響
| 項目 | ポジティブな影響 | ネガティブな影響 |
|---|---|---|
| 接客意識 | 顧客目線を意識した丁寧な対応が増える | 評価を気にしすぎてマニュアル的な対応になる |
| モチベーション | 評価が成果として認識され、やる気につながる | 不当と感じる評価に対して不満や不信感が生まれる |
| チームの雰囲気 | 接客品質への意識が全体に波及する | 「誰が評価されたのか」などの詮索がチームの空気を悪くする |
| 教育効果 | 具体的な改善点をもとにした研修が可能になる | 評価がネガティブに捉えられ、指導が萎縮につながる |
| 長期的な成長 | 定点観測により継続的な成長が見えるようになる | 調査が断続的だと場当たり的な対応に終わることもある |
ミステリーショッパーによる評価は、スタッフにとって接客を見直すきっかけになる一方で、心理的なプレッシャーの原因にもなり得ます。ミステリーショッパーの評価が「誰かに見られている」「ミスを探されている」と感じさせるものだからです。
現場スタッフは、ただでさえ日々の業務で多くの接客に追われています。そこに“匿名の誰かが評価している”という意識が加わると、普段の動き方にも影響が出てしまいます。
特に、ミステリーショッパーの調査を過度に意識しすぎると、次のような変化が見られることがあります。
- マニュアル対応に終始し、個別の顧客ニーズに対応できなくなる
- 接客中に不自然な間が生まれ、ぎこちない対応になる
- 「ミスできない」と萎縮し、声かけや提案が減る
- 誰が評価されたのかを詮索し、チーム内の空気が悪くなる
- 調査員=“敵”という認識が広がり、報告に対して不信感を抱く
こうした事態に陥ると、スタッフの信頼を失い、職場の雰囲気まで悪化してしまいます。その結果、評価どころではなくなり、接客改善という本来の目的が阻害されてしまうこともあります。
このような事態を避けるためには、評価を「数字で測られる結果」として扱うのではなく、「サービスを良くするためのヒント」として共有することが大切です。そのためには、導入前に「なぜ調査を行うのか」「評価はどう活用されるのか」を丁寧に説明し、現場との信頼関係を築いておく必要があります。
ミステリーショッパーは、運用の仕方次第で“監視”にも“成長支援”にもなるツールです。スタッフが納得し、自ら改善に取り組める状態を整えることこそが、最大の活用ポイントです。
目的・業種・導入体制で選ぶ!ミステリーショッパー会社5社徹底比較
| 社名 | サービス内容 | この会社の優位性 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| マイボイスコム株式会社 | ネットリサーチとリアルな行動を融合させたミステリーショッパー型の調査 | ターゲット層を絞り込んだミステリーショッパー型調査が可能で、全国から効率的に大量にデータ収集ができる | 店舗やサービスの利用者の声を全国で大規模に収集したい企業 |
| 日本インフォメーション株式会社 | メーカー企業を中心に様々なマーケティングリサーチを実施する総合リサーチエージェンシー | 調査内容に応じた覆面調査員を手配可能。退店後1時間以内の回答を徹底している | 店舗に潜む問題点や改善点を発見し、現場の変革を行いたい企業・店舗 |
| インパクトフィールド株式会社 | 調査項目の柔軟なカスタマイズが可能。流通小売業に強み | 自社開発のレポート閲覧システム「Market Watcher」でスピーディに調査結果の閲覧が可能 | 店頭現場のリアルを深く知りたい小売・流通系企業 |
| 株式会社MS&Consulting | 年間18.7万件超の実績。モニター選定〜レポート納品まで一貫対応 | 調査数・モニター数ともに業界トップクラス。スタッフ育成に強み | 多店舗展開で品質の標準化を目指す企業 |
| 株式会社クロス・マーケティング | 覆面調査に加え、オンライン・電話調査にも対応。自社システムあり | 業界別レポートや傾向分析にも対応。導入実績も豊富 | 飲食・美容・教育など接客品質の“見える化”を強化したい企業 |
同じ「覆面調査」という手法を提供していても、調査の強みや対象業界、サポート体制には違いがあります。
導入を検討する際は「自社が何を明らかにしたいのか」「調査結果をどう活かすのか」を軸に、最適な1社を選ぶことが成功の第一歩です。
この章では、上記5社の特徴について詳しく解説します。
マイボイスコム株式会社|ネットリサーチとリアルな行動を融合させたミステリーショッパー
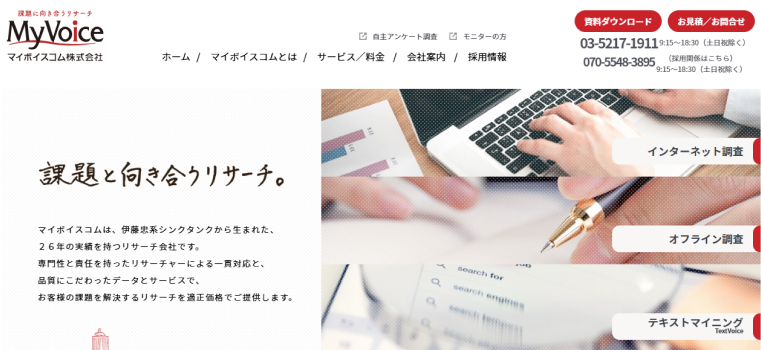
参照元: マイボイスコム株式会社
- 専門リサーチャーが調査を一貫支援
- 全国モニターによるWebアンケート回答で効率的に大量の回答収集が可能
- 大規模データによる定量的分析
- 利用者の声を全国で大規模に収集したい企業におすすめ
マイボイスコムは1999年設立の伊藤忠グループのリサーチ会社です。専門リサーチャーが調査設計からレポート作成まで一貫してサポートする「コンサル型リサーチ」を強みとしています。
マイボイスコムのミステリーショッパーは、全国のモニターに実際の店舗やイベント会場で商品購入やサービス使用を体験してもらい、Webアンケートに回答する形式で、大量にデータを集められることが特徴です。
ターゲット層を絞り込んだ調査も対応可能。店舗や施設、商品やキャンペーン評価のための利用者の回答データを大量に収集したい企業におすすめです。
日本インフォメーション株式会社|経験豊富なリサーチのプロが多数在籍

参照元: 日本インフォメーション株式会社
- 高度な専門知識を持つ経験豊富なリサーチャーが最適な調査企画を立案
- 専任調査員による柔軟で安定したオペレーション
- リサーチ課題にあった成果物(集計データやリサーチレポート)の作成力
- 複雑な調査設計や、スピード報告を求める企業におすすめ
日本インフォメーション株式会社は幅広いジャンルの調査に対応できる人材と体制を持っており、自社の課題が見えていない企業の相談先として最適な調査会社です。
2つのリクルート手法「機縁リクルート」「WEBリクルート」それぞれに大規模なネットワークを保有しており、他社では困難な条件でも対象者を探しだすリクルート能力を有しています。
相談先に迷った際には、心強い選択肢となるでしょう。
インパクトフィールド株式会社|流通・小売に強い“現場密着型”調査

参照元: インパクトフィールド株式会社
- 流通・小売業に特化した専門調査が可能
- 独自レポート閲覧ツール「Market Watcher」でスピーディに調査結果確認
- 店頭販促や陳列状況のチェックに強みを発揮
- 調査結果を元にした研修の企画・実施まで依頼したい企業におすすめ
インパクトフィールドは、店舗の「いま」をリアルに捉えたい企業に適した覆面調査会社です。
流通・小売業に特化しており、商品の陳列状況、販促物の配置、接客態度といった“店頭の現実”を的確に評価できます。
レポート閲覧ツール「Market Watcher」により、定性的な調査結果も定量化され、現場で使える形に落とし込まれる点も魅力です。
特に「販促キャンペーンの実施状況を把握したい」「現場との認識ギャップを埋めたい」という課題を抱える店舗運営者にはおすすめです。
株式会社MS&Consulting|業界屈指の実績と育成支援

参照元: 株式会社MS&Consulting
- 年間18.7万件の圧倒的な調査実績
- 調査からレポートまで一貫対応の体制
- スタッフ育成や品質均一化を重視する企業に最適
- 飲食・サービス業で悪い点の指摘だけでなく良い点を見つけて強みを強化したい企業におすすめ
株式会社MS&Consultingは、実績重視で選びたい企業にぴったりのミステリーショッパー会社です。
年間18万件以上という業界トップクラスの調査実績に加え、モニター選定からレポート納品までをワンストップで対応できる運用体制が整っています。
特に、多店舗展開している企業で「接客品質のバラつきをなくしたい」「新人研修に活用したい」といったニーズがある場合に、その力を発揮します。
調査結果をスタッフ評価や表彰制度と連動させて活用している企業も多く、育成との相性も良好です。
導入のしやすさと結果の安定性を両立させたい企業には、心強い選択肢になるでしょう。
株式会社クロス・マーケティング|チャネル横断で“体験の質”をトータル評価

参照元: 株式会社クロス・マーケティング「Shopper’s eye」
- 電話・WEB・映像など多様なチャネルに対応可能
- 業種別テンプレートとカスタマイズ設問を併用できる
- 飲食・美容・教育など接客業全般に強みを持つ
- 電話・Web含めた「顧客接点トータル」の品質を上げたい企業におすすめ
株式会社クロス・マーケティングのShoppers Eyeは、店頭対応だけにとどまらず、電話やオンラインでの応対を含めた“接客体験全体”を評価できる多機能型のサービスです。
例えば、電話予約→来店→退店後のフォローといった一連の流れをチェックするなど、立体的な調査が可能です。
業種別テンプレートと自由設計を組み合わせることで、導入初期でもストレスなくスムーズに運用が始められます。特に、ホスピタリティが差別化要因になる飲食、美容、教育業界では、「接客の質」を可視化し、強化するためのツールとして心強い存在と言えるでしょう。
顧客満足の数値化やNPS🄬改善を狙う企業におすすめです。
【2026年版】ミステリーショッパーの費用相場目安(1店舗あたり)
| 調査内容 | 費用目安(1店舗・1件あたり) | 費用の内訳イメージ |
|---|---|---|
| 来店型調査(飲食・小売など) | 15,000円〜30,000円 | 調査員実費(飲食代等)+謝礼+運営管理費 |
| 高単価サービス調査(美容・医療など) | 20,000円〜50,000円 | 体験内容が長時間かつ専門性が高いため高額傾向 |
| 電話・Web接客調査 | 5,000円〜15,000円 | 通話料+録音チェック |
| 簡易調査(撮影のみ等) | 5,000円〜 | レシート撮影や外観チェックなどの軽作業 |
| レポート作成・集計費 | 5,000円〜30,000円/調査設計単位 | 集計・分析・納品資料作成などの費用を含む |
- 費用の決まり方 上記に加え、「初期設計費(設問作成など)」として別途 5万円〜10万円程度かかる場合があります。
- 調査項目数(チェックリストの量)が多いほど、費用は上がります。
ミステリーショッパーの費用は、調査内容や業種、実費(飲食代や施術代)の有無によって大きく変動します。
例えば、一般的な飲食店の来店調査であれば、1件あたり15,000円〜30,000円程度が相場です。
一方、美容クリニックやエステなどでは、高額な施術費用(実費)が含まれるほか、専門的なチェックが必要となるため、1件で20,000円〜50,000円前後になるケースも珍しくありません。
調査設計の細かさやレポートの質は価格に直結します。
相見積もりを取る際は、単なる「安さ」だけでなく、「自社の課題を解決できるレポートが出てくるか」が重要な判断軸となります。
予算が限られている場合は、調査項目を絞った簡易調査からスモールスタートするのも一つの手です。
あとで後悔しないために!ミステリーショッパー選びの5つの注意点
- 評価項目があいまいなまま依頼すると、使えるデータが得られない
- 自社の業種に特化していない会社だと、現場とのズレが生じやすい
- 安さ重視で選ぶと、報告内容が薄く改善に活かせないリスクがある
- 調査目的を社内で共有せずに始めると、現場の反発を招くことがある
- 一度きりの調査では改善効果が見えにくく、継続運用の視点が欠かせない
ミステリーショッパーを導入する際に最も重要なのは、「なぜ調査するのか」「その結果をどう活かすのか」を最初に明確にしておくことです。目的がぼやけたままでは、調査項目も評価軸も曖昧になり、得られたデータが“意味のある改善アクション”につながらないからです。
「接客態度を確認したい」というだけでは、調査員ごとの解釈に差が出やすく、「感じが良かった」や「普通だった」など抽象的な報告で終わってしまう恐れがあります。
一方で、「声の大きさ」「アイコンタクトの有無」「説明は簡潔だったか」「案内にかかった時間」など具体的な評価軸を設定すれば、数値化・比較がしやすくなり、改善の優先順位も明確になります。結果として、現場で「どこをどう直せばよいか」がはっきりし、研修やマニュアル改訂にもつながりやすくなります。
また、自社の業種やサービス構造を理解している調査会社を選ぶことも非常に重要です。業界によって接客の“正解”は異なるため、自社の業種、サービス構造を理解している調査会社を選びましょう。
さらにミステリーショッパーの調査は単発で終わらせてしまうと「その場限り」の課題の明確化にとどまり、組織としての成長にはつながりません。
ミステリーショッパーの調査を定期的に実施することで、「同じ指摘が続いている」「改善点が反映され始めている」など、変化の傾向を把握することができます。
目的の明確化・業界理解のある調査会社の選定・定点観測による継続運用の3点は、ミステリーショッパーを“費用で終わらせない”ための鍵になります。
失敗しないために!調査会社選びのチェックポイント一覧
| チェック項目 | 確認すべきポイント | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 調査会社の業界実績 | 自社と同業種での実施経験があるか | 業界ごとの接客基準を理解していないと、評価がズレる |
| 評価基準の明確さ | 具体的な評価項目・採点基準が設計されているか | 曖昧な評価だと、現場での改善に活かせない |
| 調査員の質と教育体制 | 調査員に対して研修や評価制度があるか | 調査員のスキルで結果の信頼性が大きく左右される |
| フィードバック・報告書の内容 | 定量・定性データが含まれ、改善に活かしやすいか | 報告内容が薄いと、次のアクションに結びつかない |
| 継続支援の有無 | 単発ではなく定期調査やPDCA支援が可能か | 改善の効果検証や習慣化に欠かせない要素 |
調査会社を選ぶ際、失敗しがちなのが「価格や有名さ」だけで判断してしまうことです。自社にとって本当に効果的な調査会社を選ぶには、いくつかの上記の表のように見るべき軸があります。
まず重要なのが、業界経験。飲食・美容・金融など業種によって求められる接客の正解は異なります。自社と同じフィールドでの実績があるかを確認することが第一歩です。
次に評価軸の設計です。評価基準が曖昧だと、「で、何をどう直せば?」となり、現場で活用されません。調査項目の粒度や採点方式まで確認しましょう。
また、調査員の質も見落とされがちです。研修や認定制度が整っているかどうかで、調査結果の信頼性が大きく変わります。
報告書には定量(スコア)だけでなく定性(コメント)も含まれているか。具体的な改善策に落とし込みやすい構成になっているかも要チェックです。
単発調査では効果が薄くなるケースも多いため、定期調査やPDCAを支援してくれる体制があるかも選定ポイントの一つなので、必ずチェックしましょう。
この5つのチェックポイントを押さえておけば、自社にとって本当に意味のあるパートナーを選ぶことができます。
最後にチェック!ミステリーショッパー導入まとめ
- ミステリーショッパーとは、顧客になりすました調査員による“覆面調査”である
- 業種ごとに評価軸が異なり、調査内容は柔軟にカスタマイズできる
- 客観的なフィードバックが、接客改善やスタッフ育成のきっかけになる
- 単発より定期調査が効果的で、変化や成果の可視化に役立つ
- 導入時は調査目的・評価基準・社内共有の徹底が成功のカギになる
ミステリーショッパーは、単なる“チェック”ではなく、“成長につながる仕組み”です。この記事では、導入の目的、活用メリット、選び方、そして注意点まで網羅してきました。
次のステップは、「自社の課題は何か」「どの視点で評価してもらいたいか」を明確にすることです。具体的な目的が定まったら、比較表をもとに最適な調査会社を選んでみてください。
リサーチ会社探しにお困りなら
調査会社マッチング
貴社の課題をヒアリングし、課題解決に最適なリサーチや調査会社をご紹介するサービスです。
調査会社選びにお困りなら是非ご相談ください。
※ネット・プロモーター・スコア、NPSは、ベイン・アンド・カンパニー…の登録商標です。



