アイトラッキング調査とは?気になる相場費用・活用シーン・導入前の注意点まで徹底解説

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
Webサイトや広告の改善に取り組んでいても、「なぜ成果が出ないのか分からない」と感じることはありませんか?
ユーザーの行動には、クリックやスクロールといった行動ログだけでは見えない、ユーザーの視線の動きや無意識の注目ポイントが存在します。
アイトラッキングは、視線の流れや注視のポイントを可視化することで、ユーザーの認知行動を理解し、成果が上がらない原因を探る手がかりを得るための手法です。
UIやクリエイティブが「見られていない箇所」や「伝わりにくい要素」を、ユーザーの視線データをもとに数値と映像で可視化できます。
この記事では、アイトラッキング調査の基本から活用方法、導入のポイントまで詳しく解説しています。
アイトラッキングの実施検討中の方や相談先をお探しの方はこちらをご覧ください。
アイトラッキングの主要5社徹底比較
アイトラッキングとは?使い道と仕組みをやさしく解説

アイトラッキングの概要 5つのポイント
- 人の「視線の動き」をリアルタイムで追跡・記録する技術
- 専用カメラやセンサーで「どこを見ているか」を可視化
- Webサイト、広告、店舗レイアウトなどの改善に活用されている
- ヒートマップやゲイズプロットなどで、視線データを直感的に確認できる
- 心理学・教育・UXリサーチなど、幅広い分野で注目されている
アイトラッキングとは、簡単に言うと「人がどこを見ているのか」を測る技術です。
専用のカメラやセンサーを使って、目の動きをリアルタイムに追跡します。
例えば、Webページ上の情報やバナーがどの順番で認識されているかの可視化や、スーパーの棚に並んだ商品の中で自社商品のパッケージがどれだけ視線を集めているかを把握するために活用されます。
取得された視線データは、ヒートマップやゲイズプロットなどによって視覚的に表現され、ユーザーがどこにどの順番で視線を移動させ、どれくらい注視したかを一目で把握できるようになります。
アイトラッキングの最大のメリットは、「ユーザーが実際に見ていた場所」と「企業が注目させたかった場所」のギャップを浮き彫りにできることです。
例えば、ユーザーに読んでほしい商品説明がほとんど見られていなかったという結果が得られれば、視認性の高い配置やデザインに見直す必要があることがわかります。
このように、アイトラッキングは、感覚に頼りがちな改善施策に“客観的な根拠”を与える手法として、マーケティング、UI/UXデザイン、教育現場など、幅広い領域で活用されています。
意外と身近?アイトラッキング調査が使われている主なビジネスシーン一覧

| 活用シーン | 具体的な内容 |
|---|---|
| WebサイトのUI/UX評価 | ユーザーがどこを見ているかを分析し、ボタン配置や導線を改善 |
| 広告・クリエイティブの検証 | 瞳孔の変化を測定し、注目度が高まるデザイン等を検証。訴求力の高いクリエイティブ開発に活用 |
| 店舗レイアウト・陳列の最適化 | 店舗内で顧客がどこを見て行動しているかを観察し、導線や商品配置を最適化 |
| 製品パッケージデザイン評価 | 棚にある状態でパッケージのどこが見られているかを計測し、デザイン効果を検証 |
アイトラッキング調査を利用することで、直感や経験に頼っていたクリエイティブ改善や広告配置も、実際のユーザー視線データを基に論理的に検証できます。
バナーの視認率が低い箇所を特定したり、コンバージョンまでの導線上の「離脱ポイント」を視線から把握したりと、改善施策を検討するための根拠を与えてくれます。
例えば「なぜコンバージョンが伸びないのか?」という問いに対し、数字では見えなかったユーザーの視線の偏りが、課題の本質を示す手がかりになることもあります。
つまりアイトラッキングは、「見られているかどうか」を感覚ではなく視線データという可視化された根拠をもとに確認できる手法です。
Webサイト改善での活用
- 目的:ユーザーの視線移動を分析し、離脱要因や無視されている要素を特定
- 効果:重要な導線・ボタンの視認率を改善し、CV率向上につながる
- 注意点:被験者の環境や操作デバイスによる差を考慮する必要がある
WebサイトのUIやUXは、見た目や機能性だけでなく「ユーザーがどこを見ているか」で最適化の方向性が変わることもあります。
アイトラッキングを活用すれば、「一見使いやすそうに見える導線」が実際には注視されていなかった、といったギャップを可視化できます。
例えば、ファーストビューで重要なCVボタンが視認されていなかったケースでは、ボタンの色や配置を見直すことで、クリック率が大きく改善した事例もあります。
このように、視線データは「直感や経験だけでは気づけない課題」を発見するヒントになります。
広告クリエイティブの課題を可視化
- 目的:広告クリエイティブの注目度を可視化し、デザインの訴求力を検証
- 効果:デザインの印象や視線誘導に関する改善点を発見し、訴求力の強化に向けたヒントを得る
- 注意点:視線が集まる場所=好意的とは限らず、解釈に注意が必要
広告デザインは、色やフォントの強調、キャッチコピーの訴求力といった見た目の印象だけでは成果につながりません。
優れた広告デザインであっても視認性や視線の流れが設計されていなければ、いくら魅力的なキャッチコピーでもユーザーの意識に届かない可能性があります。
アイトラッキングを活用すれば広告のどの要素が実際に注目されているのかを可視化できます。
実際に広告クリエイティブを視線調査したところ、過度に装飾された背景ビジュアルに視線が引き寄せられ、肝心のキャッチコピーやロゴに目が向いていないことが明らかになった例もあります。
この結果を受けて、背景要素を整理し、視線の流れを意識した構成に変更したことで、注視エリアが大きく改善され、広告全体のメッセージ伝達力が向上しました。
また、複数のデザイン案を比較するA/Bテストでも、どこに視線が集まり、どこで離れているかといったユーザーの視覚的な反応の違いを捉えることができます。
アイトラッキングを活用することで、「なぜ伝わらなかったのか?」「なぜ注目されたのか?」といったクリエイティブの評価に説得力ある根拠を加えることが可能になります。
店舗の棚改善に活用例
- 目的:店舗内での視線の流れを検証し、陳列位置やPOP配置を改善
- 効果:注目されやすい棚・POPの位置を見極め、売場の改善につなげるヒントが得られる
- 注意点:リアルな購買行動との乖離を防ぐため、観察環境を工夫することが必要
実店舗における購買行動は、消費者の視線の流れによって大きく左右されます。
人は「目に入ったもの」から判断を始めるため、視認されない商品は選択肢として意識されにくくなる可能性があるからです。
アイトラッキングでは、モバイル型(メガネ型など)の非接触型アイトラッカーを使用することで、実際の購買行動に近い状態で視線の動きを計測できます。
これにより「どの棚が最も見られているか」「POPがどの位置で目を引いているか」などを可視化することが可能です。
販促のためにPOPを多く設置していた店舗でアイトラッキングを実施したところ、視線が分散して商品が注目されていなかったことがわかった事例もあります。
私たちは、自分たちが意図した通りに消費者が見てくれていると思い込みがちですが、実際には、商品ではなく装飾やコピー、背景などに消費者の視線が奪われているケースも少なくありません。
こうした傾向を正しく捉えるためには、調査シナリオの設計が非常に重要です。
被験者が「買うつもりで棚を見ているのか」、あるいは「何となく通り過ぎているだけなのか」といった意識状態の違いは、視線の動きに大きく影響します。
したがって、リアルな購買シチュエーションを模したコンテキスト設定を行うことで、より精度の高い視線データが得られます。
アイトラッキングは“人の行動を鏡のように映す”ツールだからこそ、前提条件を丁寧に作り込むことが、調査の成功を左右する鍵になります。
注目されるパッケージへの活用例
- 目的:商品パッケージの視認性と情報伝達力を評価
- 効果:ブランドロゴや訴求コピーの配置改善に活用できる
- 注意点:表示情報の多さが視線を分散させるリスクがある
店頭で消費者が目に留まった商品を手に取るまでの時間は、一般的にわずか数秒といわれています。
アイトラッキングでは、この短い時間の中で「何に目が留まり、どの情報が注目されたのか」を可視化できます。
ある食品売場でのパッケージ調査にアイトラッキングを活用したところ、最も視線が集中していたのは、期待されていたブランドロゴではなく、価格の表示部分でした。
また、スペック表記やキャッチコピーなどが詰め込まれたパッケージほど、視線が散りやすく、結果として注目されにくい傾向も見られました。
このように、アイトラッキングは、ユーザーが実際に「どこを見ていて、どこを見落としているのか」を可視化することで、パッケージデザインを改善するための重要な手がかりが得られます。
アイトラッキングの主要5社徹底比較
| 会社名 | サービス内容 | この会社の優位性 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| NeU | 検証の目的に合わせたアイトラッカーによる計測 | アイトラッキングに加えて脳活動も同時計測が可能。多面的な考察結果が得られる | 広告のビジュアルやメッセージなどのクリエイティブに改善を求める企業 |
| ヴィアゲート | AI活用で視線・表情データを含む本音(インサイト)を収集・分析 | AIインタビューと特許技術で本音データを高速・低コスト収集が可能 | 低予算・短期間で顧客の本音を深掘りしたい方 |
| 日本インフォメーション | 精度と汎用性の高い最新のウェアラブルグラスを導入 | 2008年からの調査実績。屋外・店舗・交通機関など多様な環境に対応。 | 実地検証や販促効果測定を重視したいマーケティング担当者。 |
| ナックイメージテクノロジー | 国産アイトラッカー(据置・メガネ型)の装置提供・研究支援。 | 国内自社工場による一貫生産。50年超の販売実績と技術サポート体制。 | 社内実験や教育機関での長期的な活用を想定している担当者。 |
| U-Site(イード) | UX設計やユーザビリティテストに特化したアイトラッキング調査。視線×行動の背景を組み合わせた分析。 | リアルタイム視線記録+発話プロトコルで行動意図を可視化。 | WebやUIのデザイン検証を、定性と定量の両面から改善したい方。 |
アイトラッキング調査といっても、各社が提供するサービスには対象分野・技術の深さ・分析手法のアプローチといった点で大きな違いがあります。
自社の目的に応じて選ぶことで、アイトラッキング導入の効果が大きく変わってきます。
この章では、主なアイトラッキング調査会社について詳しく解説します。
視線計測と脳計測を同時に実施「NeU」

参照元: 株式会社NeU (ニュー)
NeUは、多様なアイトラッカーを活用して、検証の目的に最適な計測を実施でき、難易度の高く深い洞察が必要な調査分析を得意としています。
特長的なのはアイトラッキングと脳計測を同時に行うことができる点で、視線の動きだけでは測れない、感情や気分を踏まえた複雑な分析が可能です。
信頼性の高さや、他社に依頼して満足な結果が得られなかった経験のある企業は、相談の価値がある一社です。
低コスト・スピーディに生体データを収集「ヴィアゲート」

参照元: ヴィアゲート株式会社
ヴィアゲート株式会社は、AI自動インタビューとスマートフォンのインカメラを使ったアイトラッキングで、顧客や生活者の「本音(インサイト)」を収集・分析するプラットフォーム「emomil」を提供しています。
従来の高額な専用機材、会場、インタビュアーが不要で、スマホ一つで24時間365日いつでもどこでも調査に参加可能なため、低予算・短期間で大量の視線データと、AIインタビューによるその理由の深掘りを実現します。
AIエージェントがデータ収集から分析、ネクストアクション提案まで自動化し、自己申告ではない真の注目箇所やコンバージョンに寄与したコンテンツを特定できる点が大きな強みです。
実地調査に強い!多環境対応の「日本インフォメーション」
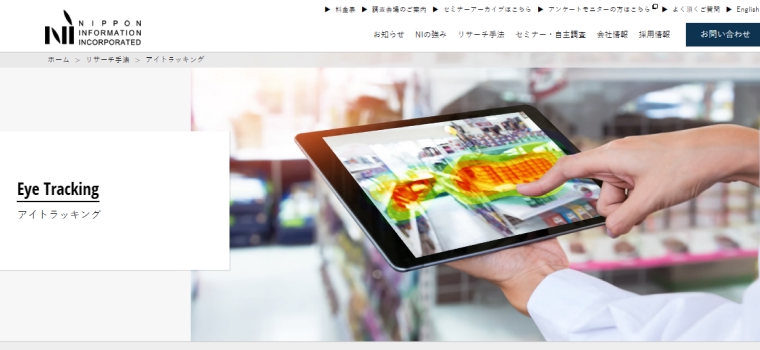
参照元: 日本インフォメーション株式会社
日本インフォメーションは、実店舗や公共空間など「リアルな環境」でのアイトラッキング調査を強みとするリサーチ会社です。
2008年からアイトラッカーを用いた調査を開始し、独自の分析手法を磨いて実績とノウハウを積み重ねてきました。
アイトラッキング調査では、軽量で動きやすいウェアラブル型のアイトラッカーを使用しスーパーの売り場や街頭での広告、実際のスーパーの店舗内など、現場での自然な視線の流れを記録します。
ウェアラブル型のアイトラッカーを使うことで、従来のアンケートやインタビューでは把握しにくかった「無意識の注目ポイント」が可視化され、客観的な評価が可能になりました。
また、アイトラッキングの視線データを、その場でのインタビューやアンケートと組み合わせることで「なぜその広告に注目したのか」「なぜそのルートを選んだのか」といった背景まで掘り下げた分析ができます。
「販促物のどこが見られているのか?」「棚の高さや動線が売上にどう影響しているのか?」といった課題を抱える流通業界やブランド企業、メーカーの販促担当者にとって、実践的で再現性のあるインサイトを提供してくれます。
より深く消費者を理解して効果的なマーケティング戦略を立てたい方には特におすすめの一社です。
装置を使いこなすなら技術重視の「ナックイメージテクノロジー」

参照元: 株式会社ナックイメージテクノロジー
ナックイメージテクノロジーは、アイトラッキング機器の国産メーカーとして、装置の導入から運用サポートまでを一貫して提供しており、その手厚いサポート体制に定評があります。
機器選定や設置後の操作方法研修、技術サポートまで一貫して提供してくれるため、初めてのアイトラッキングの導入でも安心して活用できます。
ナックイメージテクノロジーのアイトラッカーEMRシリーズ(メガネ型や据置型など)は、国内の研究機関や大学、医療現場、製造業の現場でも利用されています。
これは製造現場での作業員の視線動線分析や、医療現場での視線による手術の動作確認などに役立っています。
また、店舗での購買行動観察や教育現場での技能習得にも利用されており、例えば店舗内で顧客の視線の動きから購入の決定要因を分析したり、教育現場では視線を使って学習の定着度を測定することができます。
「自社内でアイトラッキングを継続的に運用したい」「研究や技術分析に必要な機器が欲しい」といったニーズにぴったりで、長期的に機器を活用する計画がある企業や研究機関には特におすすめです。
ユーザー体験の本質に迫るなら「イード」
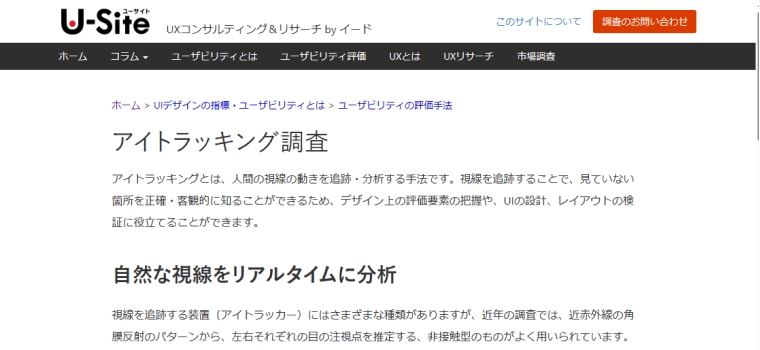
参照元: U-Site
U-Siteを運営するイードは、ユーザーエクスペリエンス(UX)やインターフェース設計(UI)に特化した専門メディア「U-Site」を長年運営しながら、企業向けにUX評価やユーザビリティ改善を支援する調査サービスも提供している企業です。
そのため単なるアイトラッキング調査会社とは異なり、「ユーザー視点での課題発見」に特化した知見と実績を豊富に持っています。
イードのアイトラッキング調査が特に強みを発揮するのは、Webサイトやアプリにおけるファーストビューの構成、ナビゲーションの流れ、情報の配置や階層構造の改善といった「操作体験全体の見直し」です。
イードのアイトラッキング調査を利用することで「ユーザーが迷わず情報にたどり着けるか」「商品ページに到達しやすいか」といったCVに直結するUX改善が可能になります。
「ユーザーの視線が迷うポイントを知りたい」というWebディレクターやUX担当者には、最適な伴走型パートナーといえるでしょう。
アイトラッキング調査費用
アイトラッキング調査の費用は、対象人数・調査内容・分析方法の複雑さによって大きく異なります。
調査の規模が大きくなるほど、準備する機材やスタッフ、分析項目、データ処理の量も増えるためです。
WebサイトのUI検証のような静的な画面上での注視ポイントを測るだけの調査であれば、比較的シンプルに設計できるため30万円前後から実施可能です。
しかし、複数のモニターを対象にした大規模調査や、脳波などの生体データと連携させて「どこを見て、どう感じたか」まで深掘りする場合は、専門機器と技術者が必要となり、100万円を超えるケースも珍しくありません。
特に、実店舗での観察やBtoC製品のパッケージテストなど、環境設定・シナリオ構築・被験者管理などの調整が複雑な案件では、調査前の設計段階から工数が増えるため、準備費用が膨らみやすくなります。
調査範囲と予算のバランスを取りつつ、費用対効果が高い設計で進めることが、成功への近道といえます。
失敗しないために!アイトラッキング調査を導入する際の5つの注意点
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 目的を明確にしておく | UI改善か広告効果検証かなど、目的によって調査設計は大きく変わります。 |
| 適切なターゲットを設定する | 実際のユーザーに近い被験者を選定しなければ、信頼性のあるデータになりません。 |
| 環境条件を整える | 照明や画面の反射、機器の設置角度など、環境次第で精度が大きく変わります。 |
| 十分なサンプル数を確保する | 人数が少ないとバイアスが生まれ、結果の一般化が難しくなります。 |
| 結果の解釈に注意する | 視線が向いた=理解・興味があるとは限らず、文脈の補足が重要です。 |
アイトラッキング調査を導入する際に最も大切なのは、「なぜ視線を測るのか」を明確にすることです。
アイトラッキング調査を導入する目的が漠然としていたり、「とりあえず試してみたい」という曖昧な理由では、調査後に得られたデータをどう活用すべきかが不明瞭になってしまいます。
また、調査に参加する被験者は「実際の利用者像に近い人」を選定することが欠かせません。年齢層や日常的に使用しているデバイスの種類(スマホ・PCなど)が異なると、視線の動きや情報の捉え方にも顕著な違いが出ます。
アイトラッキング調査を行う環境面でも、照明の明るさや被験者の座る位置、モニターとの距離といったちょっとしたセッティングの違いが、視線のブレや反応のばらつきに影響を及ぼすこともあります。
さらに、視線が向いた=興味・理解があるとは限らないため、定性インタビューや行動観察などの他手法と組み合わせて読み解く視点も重要です。
なぜならアイトラッキング調査によって得られた視線データだけでは「なぜそこを見たのか」「どう感じたのか」は判断できないからです。
だからこそ、アイトラッキング調査の導入前には「目的」「対象」「環境」の3点を丁寧に整理しておくことで、アイトラッキング調査の成果と活用価値が一段と高まります。
アイトラッキング調査で失敗しないために!
アイトラッキングは、ユーザーの無意識な視線の動きを捉えられる便利な手法である反面、調査設計や環境、対象者の選定が不十分だと、得られるデータの精度や活用効果を大きく損なうリスクもあります。
しかし、この記事で紹介した、目的設定・被験者の選定・環境条件・サンプル数・結果の読み取り方といった実践的なポイントを意識すれば、調査の成功率は格段に上がります。
自社の目的とリソースに合わせて「どの調査会社に相談すべきか?」を見極め、気になる企業があれば、まずは資料請求や相談から始めてみましょう。
アイトラッキング調査の委託先探しにお困りなら
調査会社マッチング
貴社の課題解決に最適なリサーチや調査会社をご紹介するサービスです。
調査会社選びにお困りなら是非ご相談ください。



