定性調査の基本と定量調査との違い|手法の特徴やメリット、調査会社8選

【PR】当ページは、一部にプロモーションが含まれています。
ユーザーの本音や行動の背景を深く理解するには、数字では見えてこない「人の感情・意見・考え方」に目を向ける必要があります。そこで重要になるのが、ユーザーの生の声や行動を深く理解する定性調査です。
定性調査にはさまざまな手法があり、調査の目的や得たい結果に応じて、最適な方法を選ぶことで、より効果的な調査につながります。
この記事では、定性調査のメリットや注意点、具体的な実施方法、定量調査との使い分けをわかりやすく解説します。
定性調査の委託先をお探しなら下記をご覧ください。
定性調査を成功に導く!頼れる調査会社8社
定性調査の主なメリット

定性調査には、ユーザーの本音や行動の背景を深く理解し、新しいアイデアや課題の発見ができるという強みがあります。
ここでは、定性調査の主なメリットをご紹介します。
消費者インサイトを深掘りできる
定性調査の大きな強みは、消費者の意思決定や行動の裏側にある「なぜそう感じたのか」「なぜそれを選んだのか」といったインサイトを深掘りできる点です。
定量調査とは異なり、感情や価値観、言語化が難しい見えない欲求や、数字では捉えにくい情報を丁寧にすくい取ることができます。
単なる傾向ではなく、理由に基づいたマーケティング戦略や商品改善につながります。
新たな仮説・アイデアが生まれやすい
定性調査で得られた発見は、新しい仮説やアイデアとなり、次の一手を考えるためのヒントになります。
たとえば、既存の商品に対して何となく選ばれていない理由や、ユーザー自身も言語化できていなかった不満・期待などが見えてくるケースも少なくありません。作り手側だけでは気づけなかった視点や、想定できなかった現場のリアルな声を得られます。
ユーザーの声を直接聞きながら、行動の背景やそのときの感情、選択の理由などを深く掘り下げていくことが可能です。
潜在的な課題やニーズを発見できる
定性調査では、ユーザーの行動や発言から、本人も気づいていない課題やニーズが見えてくることがあります。自由な会話や観察を通じて、日常に埋もれた不満や工夫、無意識の選択を捉えられるためです。
たとえば、明確に「不便」とは言わなくても、使いにくさを感じていたり選択に戸惑ったりしている様子が調査によって初めて明らかになるケースもあります。見えにくい課題やニーズを捉えることは、既存サービスの改善だけでなく、新たな価値提供につながります。
定性調査のデメリットと注意点
定性調査には、注意すべきデメリットや注意点もあります。
- 調査対象者が欲しいデータを持っているかどうかは、調査前に判断しにくく、適切な対象者の選定が難しい
- インタビューや行動観察など少人数で実施するため、サンプル数が限られ、結果を全体に当てはめにくい
- 集計結果が数値化されないため、調査者の深い理解と分析力が求められる
適切な設定と体制を整えることが、調査の成功につながります。
定性調査に用いられる主な手法5種類
定性調査でよく使われる手法5種類をご紹介します。
- グループインタビュー
- デプスインタビュー
- 行動観察調査(エスノグラフィー)
- アイトラッキング調査
- MROC(エムロック)
一つずつ詳しく見ていきます。
1. グループインタビュー
グループインタビューは、ユーザーの本音や潜在的なニーズを引き出す目的で実施されます。
複数の属性を持つ対象者をグループに分け、モデレーター(司会者)が進行役を担当します。グループ単位での対話を通じて、多様な視点や意見を効率的に収集できるのが特長です。また、複数のグループ間で意見の違いや共通点を比較することで、より深い洞察が得られます。
主に、マーケティングや商品開発の初期段階で有効とされる手法です。
2.デプスインタビュー
デプスインタビューは、調査対象者とインタビュアーが1対1でじっくり対話し、本音や深層心理を探っていく調査手法です。
表面的な回答にとどまらず、内面にある感情や、言葉にしにくい判断基準にまで踏み込めます。ペルソナ像の精度が高まり、商品やサービスの訴求ポイントを見直すことが可能です。
個別に深く掘り下げるアプローチのため、詳細なユーザー理解を得たい場面で特に役立ちます。
【関連記事】
デプスインタビューとは?基本手法から活用事例・おすすめ企業4社比較と費用相場も
3.行動観察調査(エスノグラフィー)
エスノグラフィーは、調査対象者の日常生活や行動を現場で観察し、深く理解するための手法です。主に「観察」と「記録」を中心に進められ、訪問観察も行動観察調査の一種になります。
単に行動だけでなく、「時間帯」「場所」「関係性」なども、丁寧に記録・分析することが重要です。なぜその行動をとったのか本人に確認し、行動の裏にある動機や価値観を探ることができます。
【関連記事】
エスノグラフィーとは?調査依頼できる会社は?調査の活用事例・調査相場を徹底比較!
4.アイトラッキング調査
アイトラッキング調査は、ユーザーがどこを見ているのかを視線データで可視化する手法です。
視線の動きや注視の位置から、無意識の関心や深層心理を読み取ります。UIや広告などの「見られていない箇所」や「伝わりにくい要素」を、数値と映像で明確に把握できるのが特徴です。
定性・定量の両アプローチが可能なハイブリッド型であり、認知行動を通じて成果が上がらない原因を探る手がかりにもなります。
【関連記事】
アイトラッキング調査とは?気になる相場費用・活用シーン・導入前の注意点まで徹底解説
5.MROC(エムロック)
MROC(Market Research Online Community)は、特定のテーマに関心を持つ人々が、オンライン上のクローズドなコミュニティに一定期間集まり、意見や行動を観察する調査手法です。
期間は1〜2カ月程度が一般的で、参加者同士のやり取りを通じて、調査設計では想定できなかった気づきやインサイトが得られる場合もあります。
定性か定量か|目的に応じた調査手法の使い分け例

定性調査か定量調査か、目的によって選ぶ手が異なります。「なぜ」を深く探るのか、「どれくらい」を把握したいのか、それぞれの違いと使い分けのポイントを見ていきます。
「なぜ」を知りたいときは定性調査
定性調査は、行動の背景にある気持ちや価値観、判断の理由など、数値では捉えきれない深層を明らかにしたいときに適しています。対象者との対話や観察を通じて、本人も気づいていない無意識の感情や意図を引き出すことが可能です。
- 仮説を抽出したい
- 原因や背景を深く知りたい
- 行動の背景にある価値観を理解したい
単なる「事実」だけでなく、その裏にある「なぜ」を知ることで、気持ちや行動の動機に迫りたいときに特に有効な手法です。
「どれくらい」を把握したいなら定量調査
定量調査は、対象者の行動や意識を数値で把握し、客観的な判断材料を得たいときに適しています。多数のデータをもとに傾向を可視化し、比較や検証を行うことができます。
- 仮説の妥当性を調査したい
- 実態や傾向を客観的に把握したい
- 判断に必要な裏付けデータが欲しい
規模や割合など「どれくらい」を知ることで、説得力のある意思決定が可能になります。
フェーズに応じて組み合わせるのが効果的
定性調査と定量調査は、調査の目的やフェーズに応じて、使い分けたり組み合わせたりするのが効果的です。
たとえば、定性調査でユーザーの本音や課題を探り、仮説を立てることで、より深い理解が得られます。その後、定量調査によって仮説を検証すれば、精度の高い意思決定が可能になるでしょう。
反対に、定量調査で得た結果の背景を深掘りするために、後から定性調査を行うケースもあります。
両者を組み合わせることで、ユーザー理解がより深まり、結果として具体的な改善策や新たなアイデアの創出にもつながります。
定性調査を成功に導く!頼れる調査会社8社
定性調査を成功させるためには、信頼できる調査会社を選ぶ必要があります。ここでは、専門的な知識がある調査会社をご紹介します。
日本リサーチセンター

参照元: 株式会社日本リサーチセンター
株式会社日本リサーチセンターは、会場調査や訪問調査などのオフライン調査と、オンライン上でのアンケートやインタビューの両方に対応しています。
ユーザー一人ひとりの日常体験に着目し、潜在的な価値やニーズを深掘りするアプローチを行ないます。また、収集した体験データから、潜在ニーズの抽出、UXコンセプトの作成・ブラッシュアップまでを一貫して支援可能です。
商品やサービスの開発初期段階における戦略設計に活かせる、実践的なリサーチを提供しています。
日本インフォメーション

参照元: 日本インフォメーション株式会社
日本インフォメーション株式会社は、高度な専門知識を持つリサーチャーが在籍し、丁寧なヒアリングを通じて企業の課題に応じた調査を設計しています。
全国に8つの自社会場を有し、会場調査や定性調査に幅広く対応できます。グループインタビューやデプスインタビュー、行動観察、ワークショップなどの多様な手法を活用し、ユーザーの本音や深層心理を引き出すことが可能です。リアルな反応をもとに、効果的な改善や戦略の立案を支援します。
プラグ
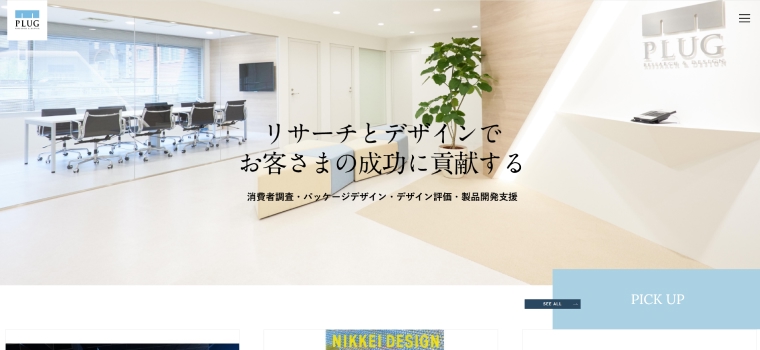
参照元: 株式会社プラグ
株式会社プラグは、30年以上にわたり多様な企業課題に応えてきた、実績ある企業です。
フルラインの調査メニューを取り揃え、「お客様のアクションにつながる調査結果を提供する」をポリシーとしています。
現象を高精度に読み解く分析力、本質を見抜く洞察力を備えたリサーチャーが在籍し、表層的な課題解決ではなく「本当に解決すべき課題は何か」を見出すところから支援します。調査後すぐに実行に移しやすいアウトプットを重視し、素早いPDCAサイクルを可能にする実用性の高いリサーチが強みです。
Quest Research

参照元: 株式会社Quest Research
株式会社Quest Researchは、リサーチャーがプロジェクトの目的達成に責任を持ち、一気通貫で調査をサポートする体制を整えています。
アンケート画面の自動生成やテストの自動化、Tableauを活用した分析効率化など、プロセス全体を徹底的に最適化することで、短期間でのアウトプットを実現しています。
最短で2日後には結果を提供できる定量調査サービスも展開しており、時間に制約があるプロジェクトや、迅速な意思決定が求められるシーンで頼れる調査会社です。
マクロミル

参照元: 株式会社マクロミル
株式会社マクロミルは、オンラインリサーチを主軸に、インターネット調査やデジタルマーケティング、データコンサルティングなど多彩なサービスを展開している企業です。
業界トップクラスの調査実績と高品質なアンケートサービスを誇り、柔軟なシステムで多様なマーケティング課題に対応しています。国内外のネットワークを活かし、データ分析から戦略立案まで、企業の意思決定を支えるサポートを行っています。
クロス・マーケティング

参照元: 株式会社クロス・マーケティング
株式会社クロス・マーケティングは、課題や目的に応じてWebリサーチを中心に、定性・定量の多様な市場調査手法を提供しています。
国内最大規模となる1,278万人超のアンケートパネルを保有し、基本属性に加えて約20のライフスタイル・購買行動カテゴリーに基づいた細かなセグメント設計ができます。
回収数の多い大規模調査から、出現率の低い条件設定の調査まで柔軟に対応できる点が強みです。海外調査や店頭での実地調査にも対応しています。
インテージ
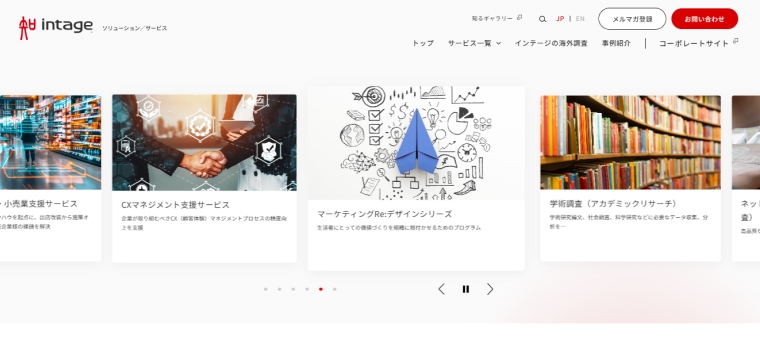
参照元: 株式会社インテージ
株式会社インテージは、生活者の深層心理を探る定性調査に強みを持つ企業です。
特に「コグニティブインタビュー」など、思考の流れをたどる調査手法を活用し、購買行動やブランド選びの背後にある価値観や無意識の判断基準を言語化します。調査から得た気づきを、マーケティング戦略や商品・サービスのコンセプト設計に活かせます。
経験豊富なアナリストが企業ごとの課題に応じた調査設計を行い、納得感のあるインサイトの提供が可能です。
アスマーク

参照元: 株式会社アスマーク
株式会社アスマークは、現場観察型のエスノグラフィ調査が得意な企業です。
自宅訪問や職場同行といった現場に足を運ぶ調査により、生活者の無意識な行動や、習慣に埋もれた不便を丁寧に可視化します。机上では見落とされがちな感情の機微や行動の文脈を捉え、より実態に即したインサイトの発見につなげます。
企業の課題や要望を綿密にヒアリングしたうえで、柔軟にカスタマイズされた調査設計が可能です。
まとめ|ユーザーインサイトを捉えるなら定性調査が有効
この記事では、定性調査の特徴や主な手法、定量調査との違いについて解説しました。
ユーザーの本音や行動の背景を捉えるには、数値では見えにくい感情や価値観に迫る定性調査が有効です。定性調査には、インタビューや観察、コミュニティ調査など多様な手法があり、調査目的に応じて適切に選ぶことで、ユーザーの深層心理や潜在ニーズを明らかにします。得られたインサイトをもとに、より実践的なマーケティング戦略につなげていきましょう。
よくある質問
| Q1.定性調査の主なメリットは何ですか? |
|---|
| 定性調査には主に以下の3つのメリットがあります。 ・消費者インサイトを深掘りできる ・新たな仮説・アイデアが生まれやすい ・潜在的な課題やニーズを発見できる 詳しくは「定性調査の主なメリット」をご覧ください。 |
| Q2.定性調査にはどのような手法がありますか? |
| 定性調査の主な手法は以下の5種類です。 ・グループインタビュー ・デプスインタビュー ・行動観察調査(エスノグラフィー) ・アイトラッキング調査 ・MROC(エムロック) 各手法の詳しい説明は「定性調査に用いられる主な手法5種類」をご覧ください。 |
| Q3.定性調査と定量調査はどのように使い分けられますか? |
| 定性調査と定量調査は、目的によって使い分けられます。 ・「なぜ」を知りたいときは定性調査 ・「どれくらい」を把握したいなら定量調査 詳しくは、「定性か定量か|目的に応じた調査手法の使い分け例」をご覧ください。 |
リサーチ会社探しにお困りなら
調査会社マッチング
貴社の課題をヒアリングし、課題解決に最適なリサーチや調査会社をご紹介するサービスです。
調査会社選びにお困りなら是非ご相談ください。



